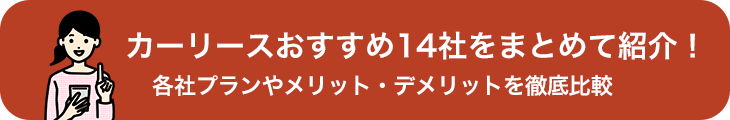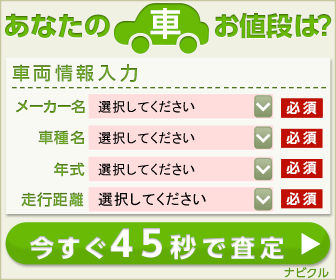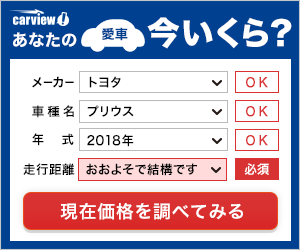自動車業界を取り巻く環境はEV化、SDV(Software Defined Vehicle:ソフトウェア定義車両)化、環境規制の強化など100年に一度といわれる変革期を迎え、サプライチェーンの再編が進んでいます。
そんななか、米トランプ政権による相互関税、自動車関税が発動されるなど、日本の基幹産業である自動車業界は大きな試練の時を迎え、日米両政府による交渉の行方に関心が集まっています。
日本の自動車業界は多数のサプライヤーに支えられており、階層化された取引構造が特徴となっているため、完成車メーカーの動向がサプライチェーンへ与える影響は大きいといえます。
調査サマリー
2024年12月時点の国内自動車メーカー10社のサプライチェーン企業数は68,338社でした。
メーカー別にみると、トヨタ自動車が最も多く40,800社、本田技研工業が22,611社、日産自動車が19,016社と続いています。
売上規模別に企業数をみると、「1~10億円未満」が過半数を占め、全体の76.4%が「10億円未満」。Tier別にみると、Tier1は「10億円未満」の企業は49.8%であるのに対し、Tier2は76.6%、Tier3以降は88.1%とTier階層が下位になるほど小規模企業が多いことをあらためて確認できます。
雇用の観点から各企業の従業員数合計をみると、サプライチェーン企業全体の436万人のうち、過半数が売上高「100億円以上」の企業に属していることが分かりました。特にTier1は従事者の82.8%にあたる182万人が「100億円以上」の企業に属しています。
※国内自動車メーカー10社
トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車、マツダ、スズキ、SUBARU、三菱自動車工業、ダイハツ工業、いすゞ自動車、日野自動車。
※サプライチェーン企業
上記「個別企業間の全取引シェアを推計するモデル」を用いて、任意の頂点企業に対して売上の1%以上を依存している企業。Tier3以降は売上高500億円未満の企業を分析対象としています。
売上高が判明した企業を都道府県別にみると、「愛知県」が11,938社と最も多く、自動車産業の中心地であることが分かります。
「東京都」(10,067社)や「大阪府」(5,598社)も多くのサプライヤーを抱えており、ビジネスや経済の中心地として関連企業やサービスが発展しています。
サプライヤーの数は各地域の産業構造や経済活動に影響されており、主要メーカーの近くにサプライヤーが集まる傾向があります。この集中により、複雑なサプライチェーン内での部品供給の効率化、物流やコミュニケーションの円滑化につながっているといえます。
Tier1トップ業種は自動車部品からソフトウェアへ
業種別にみると、Tier1は「受託開発ソフトウェア業」が402社で最多に。以下、「その他の事業サービス業」(269社)、「自動車部分品・付属品製造業」(267社)、「電気機械器具卸売業」(235社)と続きます。
Tier2は、「一般貨物自動車運送業」が2,230社でトップ、以下、「受託開発ソフトウェア業」(1,784社)、「金型・同部分品・付属品製造業」(1,001社)が上位に。
Tier3以降でも、「一般貨物自動車運送業」が1,472社でトップ、「受託開発ソフトウェア業」(482社)、「金型・同部分品・付属品製造業」(455社)と続いています。
EV化やSDV化の流れのなかで、ハードウェアに相対してソフトウェアの重要性が年々高まっています。
また、生産ラインのFA化・省力化が進んでおり、2018年時点からTier1のトップ業種は「自動車部分品・付属品製造業」から「受託開発ソフトウェア業」へ交代しています。ソフトウェアの開発力がプロダクトコストや商品力の差別化を左右する新たな時代が到来したといえます。
なお、取引構造イメージ図を示し自動車サプライチェーンの広がりを可視化したのが下図になります。
2024年の営業利益率は1.4% Tier間の差は2018年の1.3倍から4.7倍へ広がる
自動車業界は台頭する海外メーカーなどに対抗するため常に厳しい価格競争にさらされています。
そこで、サプライチェーン企業68,338社のうち、2023年4月以降の決算書分析が可能な約7,500社の製造業に焦点をあて営業利益率と営業赤字の出現率について分析を行いました。
2024年の自動車サプライチェーン製造業の本業の儲けを表す売上高営業利益率の平均は1.4%と製造業全体の平均1.8%より0.4ポイント低い結果になりました。
Tier別ではTier1が2.8%、Tier2は1.3%、Tier3は0.6%。完成車メーカー10社それぞれのサプライチェーンで同様の傾向がみられ、Tier3の営業利益率の平均がマイナスとなるメーカーも複数ありました。
2015年から3年ごとの推移を見ると、2018年はやや上昇しましたが、2021年に入ると新型コロナによる世界的混乱や半導体不足の影響で大きく低下し、2024年の時点で回復に至っていません。
コロナ禍前後を比較すると2018年は全体が3.7%、Tier1が4.3%、Tier2は3.7%、Tier3は3.4%。Tier1とTier3の差は2018年の1.3倍から2024年は4.7倍となり、コロナ禍を経て格差が広がっています。
Tier1は経済環境の変化や生産調整に比較的柔軟に対応していますが、Tier2,3では対応が十分に進まず利益率が低い傾向が見て取れました。
Tier別業種細分類TOP5に含まれる業種の営業利益率平均をみると、「受託開発ソフトウェア業」は4%超、「電気機械器具卸売業」は3%弱でした。
一方、「自動車部分品・付属品製造業」や「金属プレス製品製造業」は1%台、「金型・同部分品・付属品製造業」は利益確保できていない企業が散見されました。
※2015、2018、2021は各年1~12月決算期、2024は2023年4月以降の最新決算期
※分析対象企業は自動車サプライチェーンの製造業
2024年の営業赤字企業の出現率平均は31%、Tier1は24%、Tier2は32%、Tier3以降は35%となりました。コロナ禍の2021年から全体の営業赤字企業の出現率は3割台と高水準が続いています。
特にTierの階層が下がるほど受け身の価格設定を強いられ、コスト上昇分の価格転嫁が進まない企業は、先行きの業況が悪循環に陥る可能性が高い傾向にあり、より多くの大切な企業・人材・技術を生かす道を模索するためにも、官民が連携した取り組みが求められています。
「投資多」企業は29.3%にとどまる
製造業において、競争力を維持し、成長を実現するためには設備投資が不可欠であり、省力化やDX、新事業への参入、現地生産の推進や国内回帰といった戦略が、外部環境および企業の状況に応じて選択されます。
しかし、企業は短期的な利益確保と長期的な成長を見据えながら、設備投資と借入金の負担とのバランスを慎重に考える必要があります。
一人当たりの有形固定資産額を表す「労働装備率」を縦軸、借入金が月商の何カ月分に相当するかを表す「有利子負債月商倍率」を横軸にとり、それぞれの平均値を基準として4象限の企業数の割合を算出。労働装備率が平均よりも高い「投資多」企業は29.3%に留まりました。
内訳は自己資金主体で投資を行う「投資多・借入少(左上)」が17.0%、積極的な投資を行うが借入も多い「投資多・借入多(右上)」が12.3%に。Tier別では、Tier2の「投資多」に分類される28.6%、同様にTier3の26.4%の企業は、さらなる投資拡大や雇用の担い手となり、地域経済のけん引役として積極的に支援していく必要があると想定されます。
一方、現状維持型で堅実な「投資少・借入少(左下)」が54.1%と過半を占めました。営業利益率がコロナ禍前のレベルに回復しないなか、金利のある世界に突入し、設備投資意欲が減退している可能性があります。
「投資多」企業の事例
・毎年数億円の設備更新や先行する研究開発費など設備投資を実施(Tier1・電気機械器具製造業・売上10~100億円未満)
・高性能の試験機の導入が進んだことで収益性が改善(Tier1・計測制御機械製造・売上1~10億円未満)
・積極的なM&Aで事業拡大、自動車以外の事業部門を抱え、特定の得意先に依存しないリスク管理や未取引企業の新規開拓を推進(Tier1・潤滑剤製造・売上10~100億円未満)
・AI技術を利用した自動検査機の導入により、労働環境の改善や不良品発生を抑えるなど、効率経営を進めている(Tier2・金属プレス製品製造・売上10~100億円未満)
海外輸出企業は7,182社、トヨタが最多の5,007社
帝国データバンクが実施した『トランプ関税に対する企業の意識調査』では、中長期的な影響(今後5年程度)について「マイナスの影響がある」とする企業は44.0%でした。
自動車業界にも大きな影響を及ぼすと考えられ、なかでも特に影響が大きいとみられる、海外へ輸出をする自動車サプライチェーン企業は7,182社でした。
自動車メーカー別にみるとトヨタ自動車のサプライチェーン企業が5,007社と最も多く、次いで本田技研工業の2,968社、日産自動車の2,479社となりました。
売上規模別にみると、「10~100億円未満」が3,106社(44.7%)と最も多く、「1~10億円未満」が2,259社(32.5%)と続きました。「1億円未満」も251社(3.6%)あり、「10億円未満」の企業で2,510社と全体の36.1%を占め、輸出を手掛ける中小企業も多いことが分かります。
財務基盤が大手企業と比べて盤石ではなく、完成車メーカーやメガサプライヤーの意向に左右される中小企業からは、トランプ関税の行方に対して不安の声が聞かれます。
トランプ関税に対する企業の声
・取引先から「生産台数が減少しても耐えられる財務体質をつくる努力をするように」と言われている(自動車部分品製造)
・在庫調整や計画生産をしながら様子をみていく(金属加工業)
・完成車メーカーが関税分を負担してくれなければ赤字になる(自動車部分品製造)
・輸出関連の売上が減ると従業員を養っていけない(自動車部分品製造)
・完成車メーカーから指示がない状況なので様子見だが、現状よりも悪化する懸念がある(金属加工業)
・アメリカに輸出しようとしていた中古車が日本市場に留まり在庫が増えている(自動車小売)
※海外輸出は直接貿易、間接貿易いずれも含む
※売上未詳を除く
中国への輸出が1,563社と最多、アメリカは1,057社
輸出国が判明した企業をみると、中国への輸出が1,563社と最も多く、アメリカが1,057社と続きます。
また、多くのアジア諸国が上位に位置しており、自動車産業のサプライチェーンがアジア地域に深く根付いていることが分かります。
一方で、ASEAN諸国への相互関税率は、第一次トランプ政権時に対中追加関税回避のため生産拠点を移したことなども考慮され決定しているとも考えられます。
日米の関税交渉や2026年7月を期限とするUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の見直し交渉の行方次第ではありますが、米中対立が深まるなか、中国やアジアからの北米向けの部品は、調達先の切り替え対象となる可能性があります。
またトランプ政権の対中政策によっては、景気後退による中国企業や周辺諸国の倒産増加なども懸念材料として浮上してくる可能性も。
自動車業界は100年に一度の変革期を迎えており、2018年にはTier1のトップ業種が部品製造からソフトウェア開発に交代し、CASE領域の技術革新が進んでいます。
従来のビジネスモデルからの脱却、自動車業界への過度な依存を減らすことも重要な戦略であり、技術力を活かして異業種展開に成功している企業も存在します。
異業種展開例
・長年培ってきた樹脂加工技術を応用し、注射器や点滴の輸液バッグ部品等の医療機器分野にも参入し活躍の場を広げている(金属プレス製品製造)
・EV化に伴い、自動車向けの比率を今後減らしていく必要があるため、医療分野や建築資材分野、インフラ分野など新分野への進出により、景気動向の影響を受けにくい事業体質を構築中(工業用樹脂製品製造)
・航空機や医療など新分野への積極的な進出を図りつつ、自動車業界からの受注も得ていくことで、業容の維持・拡大を図っていく意向である(産業用ロボット製造)
・新たな事業としてフロアパネルの製造を開始している(アルミダイカスト業)
・自動車業界以外の船舶や建機、医療などの分野への進出も積極的に行っていく意向である(自動車部分品製造)
・「非自動車」の新規事業として衛生事業を立ち上げており、除菌剤消毒剤の製造・販売に着手している(鋼管製造)
2024年の自動車サプライチェーン製造業の売上高営業利益率平均は1.4%、Tier1は2.8%、Tier3以降は0.6%と、Tier間の差は4.7倍となっています。
また、営業赤字企業の出現率は3割を超え高止まりしており、各種コスト上昇に加え、下請構造や取引慣行、価格転嫁問題などが収益を圧迫する要因のひとつと考えられます。
価格転嫁については、国による下請法のガイドライン整備や価格転嫁サポート、業界団体の取り組みなどにより、交渉環境の改善が進みつつあります。
2025年3月期の完成車メーカーの売上高営業利益率は前期と比較して総じてピークアウトし、2026年3月期はより厳しい決算が見込まれますが、サプライチェーン全体の稼ぐ力が改善するよう取引適正化の進展が期待されます。
また、日産自動車の赤字決算や人員削減、工場閉鎖の発表、2025年6月11日にはTier1のマレリホールディングスが米連邦破産法第11条(チャプター11)を申請するなど、サプライチェーン企業の業況悪化が懸念されます。
足元では約30年ぶりに金利のある世界に突入し、2026年には「コロナ借換保証」を利用した約30万件、約7兆円の返済がピークを迎えるため、これにより金利負担や返済負担の増加、人手不足や後継者不足も相まってサプライヤーの経営を圧迫する可能性があります。元来、財務面が脆弱な企業においては廃業や倒産のリスクが高まる企業が増えることが予想されます。
加えてトランプ関税は自動車業界に大きな影響を与え、特に輸出企業にとっては憂慮すべき事態であり、業界として対策が急務です。関税回避のため完成車メーカーの国内生産台数の減少が続けば、受注量の減少がサプライヤーの経営を直撃します。サプライヤーとしても自助努力はもとより、各地の相談窓口、セーフティネット貸付の要件緩和、伴走支援といった政策支援の活用も必要になってくるでしょう。
環境の変化に負けず強固なサプライチェーンを築くためには、省力化や技術力確保のための投資は有効な手段となり得ます。中堅企業に対する各種成長支援策の推進も見込まれることから、投資「多」企業を中心に、サプライチェーン内の生産体制の最適化を進めるとともに、サプライヤー間の連携を強化し、生産能力や物流の効率を向上させる必要性も高まるでしょう。さらには、M&Aを通じた水平・垂直展開や事業承継など、官民が協力し設備投資と成長の好循環を生み出すことで、日本の基幹産業を守る取り組みに期待します。
出典元:株式会社帝国データバンク