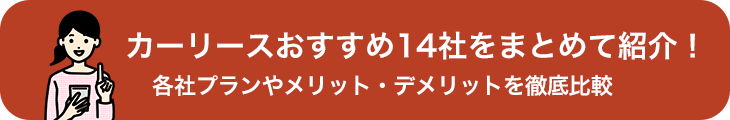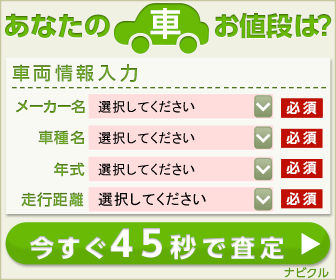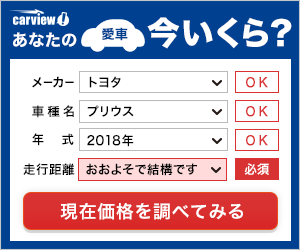DCCDとは?

DCCDとは「ドライバーズコントロールセンターデフ」と呼ばれる電子デバイスの呼称です。
インプレッサや後のWRX STIなどに採用されておりSUBARUの登録商標にもなっています。
自動車にはディファレンシャル(デフ)と呼ばれる差動装置がありますが、FRの場合はリヤに、FFの場合はフロントにあります。
そして四輪駆動車の場合にはフロントとリヤに加えてセンターデフが加えられています。
デフについて簡単に説明するとコーナリング中に左右のタイヤの回転差が生じますが、この回転差を吸収してスムースに曲がるための機構です。
センターデフの場合には前輪と後輪の回転差に対して作用するように装備されています。
DCCDはこのセンターデフの差動制限力(ロック率)を任意にコントロールすることができます。
これにより前後のトルク配分が変化したような挙動を車両に与えたりトラクション性能を走行ステージに応じて適切にコントロールすることを可能としています。
DCCDの使い方について
DCCDの使い方そのものは非常に簡単です。
コントロールダイヤルで調整するものはロックとフリーを任意に設定可能で、メーター内のインジケーターもそれに応じて点灯します。
一般的には通常の市街地走行においてはフリーにすることが多く、これはノーマルの車と同じ状態になりスムースに走行することが可能です。
一方でロック、あるいはその中間を使用するシチュエーションは限定的で、その場合には旋回時に車両がギクシャクするような挙動を示す場合もあり違和感があります。
■DCCDロック
DCCDロックはまさしくセンターデフを直結状態にするものです。
トヨタのランドクルーザーなどのようなクロカン4WDの場合にはギヤをかみ合わせるように物理的にロックするものが多いですが、DCCDの場合は電磁クラッチとクラッチ板の摩擦により作動しロックさせます。
従ってフリーからロック状態まで任意に作動力を制御可能で、完全ロックで使用するシチュエーションはダート路面や雪上など特別なトラクションを必要とする場合に限られます。
多くの場合は舗装路において完全ロックで走行するよりもパーシャルロック(中間位置)の方が適切にトラクションと旋回性能を両立することが可能です。
■DCCDフリー
DCCDをフリー状態にすると前後の回転差を吸収できる状態となりスムースな走行が可能です。
一方でトラクション性能は犠牲となる場合があります。
特殊な条件を想定すると、後輪が空転してしまった場合には本来4WDの車両としては前輪のトラクションで後輪を補うことが可能だと考えられがちです。
ところがこの回転差を吸収する機構が災いし、空転している後輪にトルクが集中してしまい車は期待通りのトラクションを得られなくなってしまいます。
スポーツ走行や競技においてはタイヤのグリップの限界領域での走行が多く、その場合にはDCCDが完全フリーの状態の場合は十分な加速が出来ない場合があります。
歴代インプレッサのDCCDについて

スバル インプレッサ(現行モデルのWRX STIも含む)は初代GC8型の誕生から現行モデルのVAB型まで4世代に渡り進化し続けています。
ライバルである三菱のランサーエボリューションは「エボX(10)」を最後に販売を終了しました。
省燃費性能とコンパクトカーやハイブリッドカー、ミニバン人気の現代においてハイパワースポーツ4WDというカテゴリーを進化させ続けたスバルの熱意は相当なものです。
そしてそんなインプレッサの進化と共に目立たないながらもひそかに進化を続けてきたのがまさしくDCCDでした。
各世代ごとのDCCDの機構の特徴を解説します。
■初代GC/GF型のDCCD
今でも名車として愛されている初代GC/GF型インプレッサは4ドア2リッターターボモデルの一部にDCCDが初めて採用されました。
1992年に登場したインプレッサでしたが、DCCD搭載モデルは1994年から販売されます。
この時すでにDCCDとしての基本機構は確率されておりシンプルな構造故に素直な特性のものでした。
一方で一切の電子制御は組み込まれておらず、サイドブレーキを操作した際に電気的にフリーになる機構を除いては完全なマニュアル操作が基本となったシステムでした。
一般的には馴染の薄いシステムであるため、ロックとフリーを操作するものの変化が良くわからなかったり有効に使うことができなかったりしたケースも多かったと思われます。
プラネタリーギヤを内蔵しフロント35:リヤ65の比率でトルク配分を行うことでフリーの際にはFR(後輪駆動)のような挙動を示し素直な回頭性と共にアクセルコントロールよるテールスライドを楽しむこともできました。
フルタイム4WDであってもサイドブレーキを引いた際にはロック時であってもフリーになる機構が組み込まれサイドターンをすることも自由自在でした。
軽量ハイパワー4WDにDCCDの電子(当時は実質的に電気デバイスというべき)デバイスが加わりGC8型インプレッサはラリーの世界においても輝かしい成績と記録を打ち立てました。
DCCDの元祖であり、現代までこの基本的な考え方は受け継がれています。
■2代目GD/GG型のDCCD
2000年にはいわゆる丸目のアプライドA~B型インプレッサに正常進化しました。
この世代は前後のトルク配分を変え45.5:54.5とよりフロントにもトルクを配分するレシオに変更されましたが、アンダーステアが強くなるなど弊害も目立ち後のアプライドC~E型では元のレシオに戻されています。
そしてその涙目と呼ばれるC型からオートモードが追加されました。
Gセンサーとヨ―レートセンサー、スロットルポジションセンサーや車速などを総合的に判断し自動的にセンターデフのロック率をリアルタイムで最適化するシステムです。
DCCDの搭載グレードも幅広く選べるようになりよりDCCDが高度なスポーツ走行用デバイスとして認知され普及した時期といえます。
その後、鷹目と呼ばれるF~G型へマイナーチェンジし舵角センサーがパラメーターとして追加されました。
DCCDの電子制御がより高度化したことでアンダー特性が解消できたことから前後トルク配分は41:59へ改められています。
また3代目インプレッサへの進化へ向けた大きな変更点として機械式LSDを内蔵するようになり電磁式よりもレスポンスを向上させグラベル路面での安定性を一層高めています。
■3代目GR/GV型のDCCD
3代目となるGR/GV型へもGDBのDCCDが継続採用されました。
メカニカル面での変化は少ないものの、制御面での進化が図られています。
特にマルチモードDCCDを新たに採用し、AUTO-とAUTO+により自動制御プログラムの強度を旋回重視のマイナスとトラクション重視のプラスへ任意に選択可能となりました。
電子デバイスが一層の進化をしたことでDCCDは街乗りからスポーツ走行や競技まで幅広く対応できるマルチなデバイスへと熟成されていきます。
■4代目VA型のDCCD
現行型のVAB型では2代目のGDBインプレッサのC型から併用されてきた機械式LSDを完全に廃止しました。
これは電磁クラッチの進化と制御技術の発達により完全に電子デバイスとして機械的要素を廃することが最大の目的です。
機械式LSDと電子デバイス(電磁クラッチ)の併用はより制御を複雑にする面もあり、車両全体としての統合制御の観点から完全な電子デバイス化へ舵を切ったものと思われます。
VAB型は高いボディ剛性と完全に熟成の域に達したEJ20型ツインスクロールターボエンジンにより重量の増加を感じさせない高次元の安定性を誇ります。
DCCDの仕組みについて

DCCDの基本的な動作原理について解説します。
DCCD機構をもつセンターデフの内部にはクラッチ板と呼ばれる摩擦板が入っており、自動車のクラッチと同様に動力の伝達と分離を行う構造になっています。
これを電気を流すことで強力なマグネットになる電磁石と組み合わせることで電気的にロックとフリーを任意にコントロールすることを実現しています。
パーシャル領域のコントロールは瞬時にONとOFFを切り替えて、その割合を変化させるPWM制御が採用されており疑似的に電圧を変化させ制御しています。
DCCDの故障事例や修理・オーバーホールについて
DCCDは比較的壊れにくいデバイスだといえます。
その理由は内部部品は複雑で部品点数が多いものの、差動原理がシンプルでそのすべてがオイルに浸された潤滑環境で行われているということです。
ランサーエボリューションに採用されているAYCと呼ばれる旋回性能を向上するデバイスは油圧により制御しているためオイルポンプの故障やデフそのものの容量不足による破損が頻発していました。
そんな壊れにくいDCCDの故障パターンはほぼ電磁コイルの断線トラブルです。
経年的な劣化によるものや瞬間的な大トルクにより電磁コイルに負荷が加わり断線することでDCCDは完全に作動しなくなりフリー状態となります。
この場合は技術やノウハウのあるショップなどで修理をするかアッセンブリーでの交換などになります。
またDCCDはすべてのモデルで電磁クラッチによる摩擦を使用しており、厳密にはディスクが摩耗するためロックするトルクが低下していきます。
一般的な使用においてはほぼノンオーバーホールで使用可能ですが、パーシャル領域など摩耗が多い使い方を多用するとトラブルやロック力の低下を招きます。
最終の6速マニュアルに搭載されたDCCDに関してはSTIから内部部品を交換するオーバーホールキットが販売されていますが、それ以前のモデルには部品供給はありません。
DCCDの後付けについて
初代モデルや2代目のモデルでは比較的簡単にDCCDを後付けすることが可能です。
DCCDはそもそも競技用途を想定したグレードにしか装備されず、それは必ずしも最高級グレードではありませんでした。
インプレッサの場合はむしろタイプRAなどの競技モデルの方がDCCDを装備するだけでなく、リヤデフサイズがR180に拡大されたりブレーキキャリパーが対向タイプになるなどスポーツカーとしての装備は充実していきます。
DCCD非搭載モデルにDCCDを後付けする場合にはトランスファーと呼ばれるセンターデフが入ったトランスミッションの後端部を交換します。
またそこに電圧をかけることでロック制御をすることが可能です。
簡易的に12Vを流すことでロックとフリーをコントロールすることも出来ますが、基本的には制御ユニットとインジケーターも移植することが一般的です。
それより後のモデルの場合は電子デバイスがより高度化したことで制御系が複雑になり簡単には移植できません。
しかし異なる部品をすべて入れ替える形をとれば移植することは可能です。
DCCDのチューニングについて
DCCDのセンターデフユニットそのものは初代から現行モデルまで大幅には変わっていません。
制御系こそまったく異なりますが、フリーとロック、そしてその中間をコントロールしています。
GDB型インプレッサの途中からオートモードが追加されましたが、そのオートモードを初代インプレッサなどにも機能させるアフターパーツが市販されています。
これはDCCDのセンターデフユニットには改造を加えることなく、車速やGセンサーなどを元にロックするための電気的な制御を連動させコントロールするデバイスです。
減速旋回時にはフリー寄りにしてスムースに旋回させ、加速状態になったらロック方向へ調整することで絶大なトラクションと旋回性能を両立することも可能です。
さらに高機能なコントローラーはDCCDの制御マップ(入力と出力の変化を決めるもの)を自由にパソコンでセッティング可能なものまであります。
DCCDそのものに関してはコイルの巻き数を増やしたり、内部の摩擦ディスクの厚さを増やすなど強化する改造を行うショップなどもあります。
基本的には改造することは出来ないDCCDですが、制御系のコントロールや強化などのカスタムは現在でも行われています。
まとめ
スバル独自のDCCDはインプレッサの進化と共に発展してきました。
スバルの最大の魅力は水平対向エンジンによる重心の低さとシンメトリカルAWDと呼ばれるバランスの良いフルタイム全輪(4輪)駆動の組み合わせです。
その武器をさらに高次元のものへ進化させ「スポーツ4WD」とも言える圧倒的なコントロール性能を与えているものがこのDCCDだといえます。
本格的なダート走行はなかなか気軽に体験することは難しいですが、クローズドコースでの雪上走行や氷上走行においてはDCCDを駆使した4輪のトラクションをフルに生かした走りを誰もが体感することができます。
スバルの四輪駆動の魅力は奥が深く、DCCDはきってもきれないデバイスだといえます。