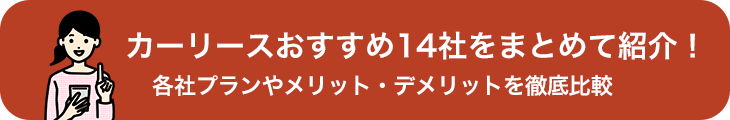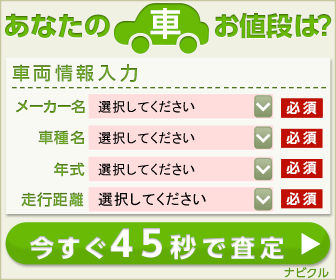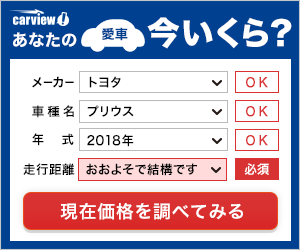トヨタが作る「次世代タクシー(JPN TAXI)」とは
トヨタ自動車が2017年から導入する次世代タクシー(JPN TAXI)は、日本の街の風景を変えることを念頭に、「おもてなしの心」を反映した内外装デザインを採用し、また、安心・快適性能を持たせることで、環境負荷低減、超高齢化などの社会変化に対応した、新たな「日本のタクシー」を目指して開発された車両です。

トヨタ 次世代タクシー(JPN TAXI)
機能はタクシー業界の声が大きく反映され、広い車内には車イスが乗せられ、エアコンは運転手だけでなく乗客も管理できるなどの工夫がされています。また自動ブレーキが搭載されることや、LPガスのハイブリッド車になっているなど、年間で10万キロとも言われる長距離を走るタクシーにとって、有効な仕様になっています。
2017年に発売を予定しており、実際には10月ごろから街中を走るとみられています。
■2013年の東京モーターショーでお披露目
次世代タクシーは『JPNタクシーコンセプト』として、2013年の東京モーターショーでお披露目されました。
ドライバーがプライドを持って仕事が出来るようデザインされ、その外観や内装は量産機でもほぼ踏襲されています。

トヨタ・JPNタクシーコンセプト(東京モーターショー13)
「おもてなしの心」を反映したデザイン
この次世代タクシーは「ロンドンに山高帽を被ったまま乗れるようにと背高デザインが採用されたロンドンタクシーがあるように、日本のタクシーも日本に似合ったもの、日本の風景を作るものであるべきだという」フィロソフィーによって開発が進められました。
トヨタは「日本らしいタクシー」というテーマの回答を「おもてなし」に求めました。
安全、安心、環境にやさしい、健常者からハンディキャップまでさまざまな人が同じように使うことができ、乗り降り自体もきわめて楽に行えるといった特性は、すべてこのおもてなしの精神に収斂するものであるといいます。

■テーマカラーは「深藍(こいあい)」
街にあふれ返り、どこでも目にするタクシーは、風景作りにも一役買うべきだという考えから、テーマカラーも設定されています。それは、明治時代に日本を訪れる欧米人がジャパンブルーと呼んだ「深藍(こいあい)」です。
実際には法人タクシーはタクシー会社のコーポレートカラーに塗装されてしまうケースが大半であるため、あくまで理念的なものにとどまると思われますが、新型タクシー開発陣の心意気が垣間見えるポイントといえるでしょう。

■車高は高く、車長は短く
次世代タクシーのボディサイズは全長4400×全幅1695×全高1740mmとなっており、タクシーの区分では小型車規格に相当します。
トヨタの現行タクシー専用モデルは3機種あり、車格が高いほうから順に『クラウンセダン』『クラウンコンフォート』『コンフォート』というラインナップです。ボトムエンドのコンフォートと比較して全幅は変わらず、全長は190mm短く、全高は215mm高くなっています。

トヨタ クラウンセダン

トヨタ クラウンコンフォート
現行車種に比べ全長を大きく切り詰められていますが、これは乗り場の車列を短くすることも期待されています。
■ユニバーサルデザインに配慮
次世代タクシーのパッケージングは、乗客の乗降のしやすさというユニバーサルデザインを意識して作られています。
リアドアの開口部は天井近くまで縦方向にきわめて広いくなっており、身長の高い人はもちろん、腰をかがめるのが負担になる高齢者、妊婦、ハンディキャップなど、さまざまな乗客が乗り降りしやすいようデザインされているます。
また、助手席を前に倒せば、なんと車椅子を人が乗った状態のまま車内に収容することも可能とのことです。

車椅子も乗り込むことが可能
自動ドアとなる左側のリアドアは今日のタクシー車両の主流であるスイングドアではなくミニバンのようなスライドドアになっており、ドア開閉に必要な路肩のスペースは今より格段に小さくなり、乗り降りもしやすくなりそうです。


シートバックにあるグリップはどこでも掴めて、伝わりながら室内に入ることが出来るようにしてある。そこにある黄色いマークは、立ち上がった状態では良く見え、シートに座ると隠れて見えなくなるよう工夫がなされている。
■広い収納スペース
次世代タクシーは現行車種に比べ全長は短くなるりますが、荷室は長期旅行用の大型トランクが2個平積みできるだけの容積が確保されています。

日本は現在、海外からの観光客を増やす政策を打っており、2020年には東京オリンピックも開催されます。国際空港に到着した海外からの旅行客の送迎にも使えるようにという配慮が設計段階でなされたそうです。
パワートレインは2モーター式ハイブリッド
燃料は現行のタクシー専用車に多い液化石油ガス(LPG)ですが、パワートレインはコンベンショナルなレシプロエンジン+変速機ではなく、エンジン、発電機、走行用モーターを遊星ギアで連結した2モーター式ハイブリッドで、走行中の燃費は現行タクシー車両に比べて大幅に向上する見通しです。

タクシーは客待ちなど、アイドリング状態で停止する時間が長くなる傾向がありますが、2モーター式ハイブリッドは停車中もサービス電力が大型蓄電池から供給され、エンジンは電力が不足してきたときに発電のために起動させるだけですみます。
これにより、客待ち時の燃料消費量を大幅節約するという効果も期待できそうです。
プライドを持って運転してもらえるように
インテリアを見ると、運転席とそれ以外とでカラーが違うことに気付く。トヨタ自動車東日本デザイン部第2デザイン室第1デザイングループグループ長の堀田達也さんによると、「プロの仕事場というイメージであえて変えている」そうです。


安全機能「トヨタ・セーフティー・センスC」搭載
次世代タクシーは自動ブレーキシステムを初めとするトヨタの安全機能パッケージ「トヨタ セーフティー・センスC」を搭載しています。

トヨタ セーフティー・センスCには
・衝突回避支援または被害軽減を図る対車両の自動ブレーキ「プリクラッシュセーフティシステム」
・車線を逸脱アラートでお知らせする「レーンディパーチャーアラート」
・ハイビーム/ロービームを自動で切り替える「オートマチックハイビーム」
が含まれており、搭載をしているカローラなどはJNCAP予防安全性能評価において、高得点で最高ランクの「ASV+」を獲得しています。
次世代タクシー普及の見通しは
次世代タクシーは、現行タクシー専用車『コンフォート』および『クラウンコンフォート』の代替がターゲットになり、そのクラスの代替は年間1万5000台程度で、新型タクシー専用車の生産スケールも同程度になると予想されています。
2017年1月に開催された「国際自動車通信技術展」で配車アプリ「全国タクシー」の導入など、業界のIT化を推進し注目を集める“タクシー王子”こと日本交通の川鍋一朗代表取締役会長が登壇し、次世代タクシーについて、「価格は高いが東京都にかけあい多額の予算も頂いた。2020年までには3台に1台(1万台程度)が必ずこの車両になります」と熱っぽい口調で語っていました。

“タクシー王子”の異名を持つ日本交通の川鍋一朗代表取締役会長
因みに「おもてなし」をコンセプトに開発された次世代タクシーですが、オリンピック招致の“お・も・て・な・し”以前にこのワードは決定していたとのこと。
2017年10月ごろから実際に街を走るとみられている次世代タクシー(JPN TAXI)、見かけた人はぜひ「おもてなし」を体験してみてください。