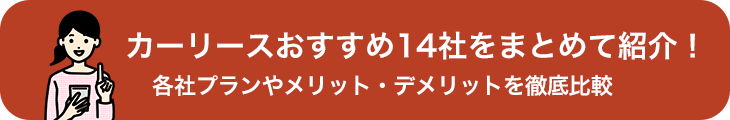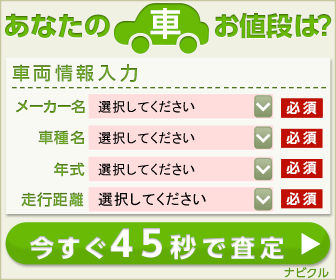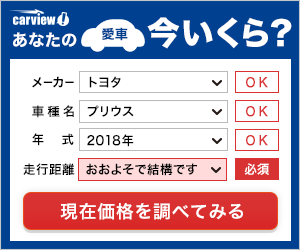タイヤ交換の重要性
《画像提供:Response》タイヤ交換の重要性
タイヤはゴムでできているため、使っているうちに劣化します。また、道路と接地しているので、走行中や発進・停止時に摩耗していきます。そのため、車を運転している中で以下のようなトラブルの原因となり、注意が必要です。
■燃費や快適性の悪化
タイヤは元々やわらかいゴムでできていますが、走行などによってすり減り、タイヤの表面が固くなっていきます。そうなると、タイヤが衝撃や振動を吸収しにくくなり、走行時の快適性が下がってしまうのです。
さらに、タイヤがすり減ると、同じ走行速度でもエンジンの回転数が上がるため、燃費が悪化します。「走れているから大丈夫」と思ってしまいがちですが、長く同じタイヤで走り続けていると、走り心地が悪いと感じたり、燃費が落ちる場面が出てきます。
■事故の要因になる
やわらかいゴムで作られているタイヤは、使い続けると表面が固くなって滑りやすくなります。タイヤが滑りやすくなると起こるのが、スリップです。
他にも、タイヤの骨格を形成する部分であるカーカスが破裂してしまい、バーストの原因にもなります。スリップやバーストは、周りの車も巻き込む事故に発展する可能性もあり、とても危険です。
■タイヤの溝が1.6mm未満は法律違反
タイヤの使用限度を示す「スリップサイン」が露出する残溝は、1.6mmです。一部でも残溝が1.6mm未満のタイヤは整備不良と判断され、道路運送車両の保安基準違反になります。
安全や法令順守のためにも、点検の際には目視でも残溝の状態を確認しましょう。
タイヤ交換の目安は?

タイヤ交換の目安は?
タイヤにも消費期限があります。タイヤメーカーでは、走行距離3~4万km、製造から4〜5年を交換の目安としていますが、走行距離や、使用状況などによってはさらに短くなることも。
タイヤの種類によって目安も変わってくるので、以下を参考に交換時期を検討してください。
■ノーマルタイヤ
《画像提供:Response》ノーマルタイヤ
ノーマルタイヤの寿命の目安は、一般的に製造から4〜5年とされています。走行距離にすると、約4万kmです。
寿命と走行距離の両面から、交換時期を検討しましょう。
■オールシーズンタイヤ
《画像提供:Response》グッドイヤー アシュアランス ウェザーレディー(参考画像)
オールシーズンタイヤの寿命の目安も、製造から4〜5年程度といわれています。走行距離だと3万km〜5万km程度です。
走行距離に差はありますが、道路状況や使用頻度によって差があるので、3万kmが近づいてきたら一度様子を確認したうえで、交換時期を検討するのがよいでしょう。
■スタッドレスタイヤ
《画像提供:Response》ミシュラン X-ICE SNOW
スタッドレスタイヤの寿命の目安は、製造から3〜4年といわれています。
他のタイヤよりも交換時期が早いのは、ゴムが柔らかく、劣化しやすいため。3シーズン~4シーズン程度での交換が推奨されているので、タイヤの状態が良くても、時期が来たら交換を検討しましょう。
いますぐタイヤ交換するべきサイン
タイヤ交換は、使用年数や走行距離だけで判断できるものではありません。以下のようなサインが出てきたら、タイヤ交換を検討しましょう。
■スリップサイン
《画像提供:Response》スリップサイン
スリップサインとは、タイヤの溝が1.6mm以上残っているかを確認できるサインです。前述の通り、タイヤの溝が1.6mm以下は道路交通法違反になります。
新品のタイヤの場合、溝は約8mmが一般的です。タイヤのゴムは走ることで摩耗し、溝も減っていきます。
スリップサインの確認は難しいものではありません。タイヤ側面にある三角形マークの延長線上の溝に設置されているのがスリップサインです。
タイヤによって4〜9箇所確認場所があるので、愛車のタイヤのどこにスリップサインが設置されているか確認しておきましょう。
■キズ・ヒビ割れ・摩耗
サイドウォールはタイヤの側面のことで、タイヤのメーカー名や、サイズ、速度記号といった情報が印字されている部分です。
走行中のタイヤの変形がもっとも大きい部分でもあります。そのため、サイドウォールにひび割れや、キズ、摩耗などをみつけた時は要注意です。
サイドウォールの機能のひとつとして、走行中にたわむことで乗り心地を良くしたり、タイヤのグリップ力をキープしたりする効果があります。
しかし、このたわみが原因で、少しの傷が深く広い範囲に広がることもあります。傷が大きくなるとパンクやバーストの原因にもなり大変危険です。小さな傷でも、走行中の負担で急に広がることもあるので、早めに交換をしておきましょう。
■走行距離3万kmが目安
タイヤの寿命は、人によって乗る頻度や走行距離が違うため、使用年数だけでは決められません。そのため、使用年数だけで判断するのではなく、走行距離でもタイヤの交換を検討するようにしましょう。
運転期間が短期間でも、長距離の走行や乱暴な運転をすると、タイヤの寿命は短くなります。消費期限前でも、走行距離が3万km〜3万2,000kmになると、交換が必要なほどのダメージを受けていることもあり得ます。走行距離が3万kmを超えたら、交換を検討しましょう。
■使用年数
タイヤには、側面に製造年週が表示されていますが、消費期限は明記されていません。
製造年週がわかっていても、消費期限の設定ができないのは、保有者により車の使用状態、運転方法、車の保管状況が異なり、タイヤの劣化スピードも変わってくるのが理由です。
砂利道、下道走行が多い車や、常に荷物を多く積んでいる車はタイヤの減りが早くなります。
■ロードノイズ
ロードノイズとは走行中に車内に伝わる騒音のことです。悪路や舗装されていないような凸凹道を走行すると発生しやすくなります。
ロードノイズがこれまでより大きくなってきたら、原因のひとつにタイヤの劣化によるものもあることを覚えておきましょう。
タイヤ交換の方法と費用の目安

タイヤ交換の方法と費用の目安
タイヤ交換にはさまざまな方法があります。タイヤをそのお店で購入し作業してもらう方法、タイヤをネット購入し、持ち込み作業のみをプロに依頼する方法などさまざまです。
値段設定はお店によって異なるため、依頼する前の確認が重要になります。値段の目安は下記を参考にしてみてください。
■タイヤ専門店
タイヤ専門店に依頼した場合の参考費用はこちらです。
・購入+作業の場合 8,000円~13,000円程度
・作業のみの場合 12,000円~30,000円程度
タイヤ専門店は、タイヤ交換の工賃が比較的安く設定されています。さらにタイヤのプロであるため安心して依頼できる点もメリットです。
専門店は、タイヤ購入と交換がセットの前提で価格設定していることが多く、持ち込みでタイヤ交換のみを依頼すると、作業工賃は平均よりも高くなる傾向があります。
■カー用品店
カー用品店に依頼した場合の参考費用はこちらです。
・購入+作業の場合 6,000円~8,000円程度
・作業のみの場合 8,000円~15,000円程度
タイヤ交換の工賃を抑えた料金設定になっていることが多いのが、カー用品店です。
ただし、カー用品店は作業ピットが混雑していることも多いため、事前予約をしても、ある程度の待ち時間は覚悟しておきましょう。
■ガソリンスタンド
ガソリンスタンドに依頼した場合の参考費用はこちらです。
・購入+作業の場合 4,000円~20,000円程度
・作業のみの場合 8,000円~25,000円程度
ガソリンスタンドは、他の業者よりもタイヤ交換の工賃が安く設定されている傾向があります。近くに対応してくれるスタンドがあれば、すぐに行けるという点もメリットでしょう。
しかし、すべての店舗がタイヤ交換作業に対応しているわけではないことや、交換可能なタイヤサイズが限定されている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
■ディーラー
ディーラーに依頼した場合の参考費用はこちらです。
・購入+作業の場合 8,000円~32,000円程度
・作業のみの場合 12,000円~50,000円程度
ディーラーでは、他の業者に比べてタイヤ交換工賃が高く設定されています。また、持ち込みタイヤはNGのところがほとんどです。そのため、タイヤ持ち込みについては事前の確認が必須となります。
■自分で行う(セルフタイヤ交換)
自分でタイヤの交換ができれば、空いた時間に好きな場所でタイヤ交換をでき、費用も抑えられます。また、パンクなどで急遽タイヤ交換が必要になったときにも対応できます。
タイヤ交換は専門店に依頼するだけではなく、道具を揃えさえすればセルフでもタイヤ交換ができますが、交換にあたっては、ジャッキやタイヤストッパーなどの機材の準備も必要です。
工賃がかからないというメリットはありますが、初期費用だけで考えると、専門店やカー用品店に依頼するよりも割高になるので、一度だけの交換ではなく、長期的にセルフタイヤ交換を検討している場合に適しています。
タイヤ交換は、ホイールもセットになっているものの交換と、タイヤゴムのみの交換では作業内容が大きく異なります。
一般的に、ネット記事などで取り上げられるセルフタイヤ交換は「ホイールにすでにタイヤゴムが取り付けられている」タイヤなので、すべてのタイヤが該当するわけではありません。
タイヤのゴム部分だけを交換するには、さらにタイヤチェンジャーという専用の機材が必要です。手動で作業するものでも数千円〜数万円、電動のものだと数十万円するものもあるため、ゴム部分だけの交換もセルフで対応するのは上級者向けの作業といえます。
持ち込みでのタイヤ交換を依頼するときの注意点

持ち込みでのタイヤ交換を依頼するときの注意点
専門店に自身でタイヤを持ち込み、タイヤ交換を依頼する際にはいくつかの注意点があります。
まずは、持ち込みのタイヤが車体に合うかどうか。素人目に見ると、タイヤはどれも同じように見えますが、もちろん違いがあります。
タイヤ選びの際は性能にばかり目が行きがちですが、どれだけ高性能でもサイズが合っていなければ取り付けられません。タイヤは返品や交換ができないケースもあるので、サイズをしっかり確認してからを購入しましょう。
次に持ち込みに対応しているかどうか。店舗としては、タイヤ購入での利益をメインとしていて、交換はサービスに近い形で料金設定をしているところもあります。
タイヤ交換をしているからといって、すべての店舗が持ち込みでも作業してくれるわけではありません。持ち込みに対応しているかは、事前に必ず確認しましょう。
持ち込みの可不可とあわせて確認したいのが料金について。こちらも店舗でタイヤを購入したときと、持ち込みとでは交換料金が変わるところもあります。
作業後に「思ったよりも高かった」とならないよう、事前の確認が大切です。
セルフタイヤ交換に必要な工具と手順
《画像提供:Response》セルフタイヤ交換に必要な工具と手順
ご自身でセルフタイヤ交換をする際には、必要な工具がいくつかあります。途中で作業が止まらないようにするためにも、すべて揃えてから作業を始めましょう。
また、タイヤ交換の際に手順を間違えないよう、事前に作業の流れを確認しておくことも大切です。
■タイヤ交換に必要な工具
タイヤ交換に必要には、下記の工具が必要です。
・ジャッキ(車を持ち上げる道具)
・ホイールキャップレンチ、またはマイナスドライバー
・作業用の軍手や手袋
・車の輪止め(車が動かないようにする道具)
・レンチ(ナットを緩める・締める道具)
・空気圧計
■タイヤ交換の手順
タイヤ交換の手順ですが、まずはじめに安全なところに車を停め、輪止めで車が動かないようにしてから作業を開始します。
1.ナットを緩める
2.ジャッキアップポイントにジャッキを当て車体を上げる
3.ナットを外してタイヤを取り外し、新しいタイヤに付け替える
4.ジャッキで車体を下ろし、ナットをしっかり締める
こちらがタイヤ交換の大まかな流れになります。では、具体的な作業内容をみていきましょう。
1. ナットを緩める
まずはナットを緩めます。タイヤ交換のためには車体を持ち上げますが、持ち上げた後だとホイールを緩めるのが大変になるので、先にナットを緩めておきます。
多少ナットを緩めたくらいでは、タイヤが外れることはないので安心して作業を続けてください。
2.ジャッキアップ
ジャッキアップとはジャッキを使い、タイヤの一点に力を加えて車体を持ち上げることをいいます。
このときジャッキを、ジャッキアップポイントと呼ばれる車体が補強してあるポイントに当て、ジャッキ専用の棒を穴に差し込み、回して車体を上げます。
ジャッキアップポイントの場所は車種によって違うので、作業に入る前に確認しておきましょう。
3.タイヤを交換する
レンチでナットを回し、交換するタイヤを外します。ボルトとホイールの位置を必ず確認してから、新しいタイヤを取りつけましょう。
新たなタイヤを車体に取り付けたら、ナットを全箇所にはめ込み、レンチで締めます。このとき、ナットを逆さにつけないよう注意し、対角線上に締め付けていくようにします。
タイヤを左右前後に動かしガタつかなければ、ジャッキダウンします。
4.仕上げの増し締めする
工程を繰り返し、4本ともすべて交換し終わったら、最後にナットの増し締めをします。
■セルフタイヤ交換時の注意点
セルフでタイヤ交換をする際ですが、作業は砂利道などもなるべく避け、必ず平らな場所で行いましょう。作業がしやすいのはもちろんですが、車体が傾くなど作業中のトラブルを避けられます。
また、交換後はタイヤの空気圧のチェックやお試し乗車をしておきます。見た目は問題なくても、走ってみるとうまくセットできていなかったり、タイヤに不具合があったりするケースもあるためです。
最後に、タイヤの保管場所について。タイヤは置いているだけでも劣化していきます。そのため、タイヤの保管場所には気を付けましょう。そのまま置くのではなく、カバーをつけておくことも劣化には効果的です。
タイヤの寿命は延ばせる!?
タイヤは地面と直接触れるものなので、安全に走るためにも時期が来たら交換が必要ですが、交換には費用がかかります。少しでも長く、良い状態で乗れるようにするためのポイントを紹介します。
■目視点検
タイヤを見て、傷やひび割れ、減り具合、タイヤの側面に異様な膨らみが無いかなどを目視で点検することを目視点検といいます。安全確認のひとつであり、交換時期を見極めるためのものです。
また、日常的に目視点検を続けていると、自分の走り方のクセや、タイヤの傷みがどういうタイミングで出るのかを知ることができます。走りのクセや傷みが出るタイミングがわかれば予防策も取れるので、寿命を延ばすことにもつながるのです。
■適正空気圧
適正空気圧
適正空気圧は車種によって異なります。空気圧は運転席側のドア付近または、給油口に貼付された空気圧表示シールで確認することができます。
空気圧はいつの間にか低下しているので、定期的に確認してみましょう。タイヤの寿命を延ばすだけでなく、快適性も高まります。
■タイヤローテーション
タイヤローテーションとは、タイヤの前輪と、後輪の偏摩耗を防ぐために、定期的にタイヤの位置を交換することです。
定期的に、タイヤローテーションをすることでタイヤの摩耗を防ぎ、寿命も長くなります。ディーラー車検などでは、タイヤの状態を見てローテーションをしてもらえることもあります。
■シーズンオフタイヤの適切な保管
タイヤは、適切な保管方法で保管しなければ劣化が進んでしまいます。
保管前にタイヤの汚れを落とし、泥や砂、化学物質や油汚れなどがタイヤについてないことを確認し、タイヤの劣化を防ぐために洗剤などは使わず、なるべく水だけで洗いましょう。
水洗い後は、カビなどを防ぐために水分を拭き取りしっかり乾燥させます。乾燥後は、防水性の高いカバーをかけ、なるべく日陰で紫外線や雨からタイヤを守れる場所に保管します。
また、エアコンの室外機などのオゾンが発生する機器の近くでの保管は避けましょう。
■安全運転
《画像提供:Response》安全運転
運転時の急な加速や急ブレーキ、急カーブなどはタイヤにとって負担がかなり大きいといわれています。そのため、急ブレーキや急発進をしないことなどを意識して、タイヤにとって優しく、ご自身にとっても安全な運転を心がけましょう。
まとめ

まとめ
車を動かすうえで、タイヤはとても重要なパーツです。タイヤは、小さな接地面で重たい車体を支えています。間違えた扱い方で乗り続けると、それが事故の要因ともなり得ます。
タイヤの安全を保つためには、正しい時期でのタイヤ交換が大切です。専門店への依頼だけでなく、セルフでもできるタイヤ交換は、ご自身の求めるものや、メリットとデメリットを比べてみたりと、それぞれに合った方法を選択するのがよいでしょう。