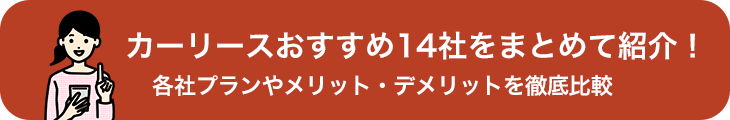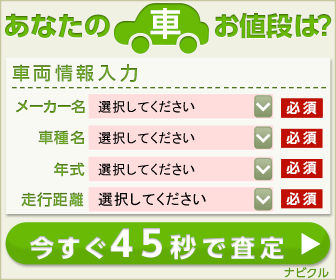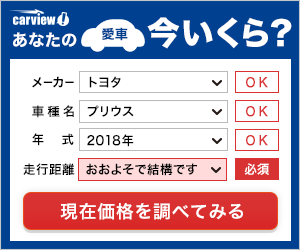ボルボ 262C、生誕40周年…人々の認識を変えた2ドアクーペ

正直、めっちゃかっこよすぎませんか?
ボルボ初の2ドアクーペ『262C』が今年、生誕40周年を迎えます。
ボルボは1974年秋、260シリーズの最初のモデルとして『264』を発表し、2年後にはボルボ初の6気筒エステート『265』がデビュー。両モデルが好調な販売を続ける中、ボルボは1977年、ジュネーブモーターショーで262Cを披露しました。

262Cは、Aピラーを大きく傾斜させるとともにルーフの位置を60mm低くし、流麗かつスポーティな2ドアクーペとして登場。
インテリアには、レザーとハードウッドを贅沢に使用し、シート、ヘッドレスト、ドアサイド、ステアリングまでもがレザー仕上げとなっていました。


ボルボ1800ES
ボルボは、1973年に『1800ES』が生産終了となったあと、後継の2ドアスポーツモデルは不在となりました。
ボルボ最大の輸出市場である米国で、2ドアクーペの人気は高く、当時のペール・G. ジレンハマーCEOは、これを問題と捉えていたんだとか。
さっそく、ボルボのチーフデザイナーであったヤン・ヴィルスガールドは262Cのデザインに取り掛かりました。262Cの形をスケッチで描き、インテリアは『164』を使用して試作。

ボルボ164
イタリアのカーデザイナー、セルジオ・コッジョラにデザイン案は持ち込まれ、4ドアだったボディは、ルーフの位置を低くした2ドアボディに変更。さらに、ルーフは樹脂性のカバーで覆われ、ワイドなCピラーにはスウェーデン国を象徴する紋章である3つの王冠が取り付けられました。
気になるパワーユニットは?

パワーユニットは、260シリーズ全モデルで採用する2.7リットルV6「B27E」エンジンを搭載。
プジョー、ルノーと共同開発した同エンジンは最高出力141hpを発生、アルミニウム製のエンジンブロックとシリンダーヘッドを採用したことにより、重量を150kg以下に抑えています。生産はイタリアのベルトーネが請け負いました。その理由は生産台数が少なく、イェーテボリのボルボの工場に適していなかったためで、フロントウインドウの下端にあしらわれた小さなエンブレムがベルトーネ生産であることを示しています。
発売当初の数年間、262はブラックの樹脂性カバーのルーフを備えたシルバーメタリックカラーのみだったが、1979年以降は、ルーフなしのゴールドメタリックカラーを追加。
1980年には、樹脂性カバーのルーフを備えたブラック、ライトブルーメタリック、およびシルバーメタリックカラーがラインナップから外されました。
そして時代は1981年へ…

そして1981年、シリーズ中で最も際立つ存在となった最終モデルが登場。よりスリムになったバンパーと新デザインのヘッドライトなど、外観の大幅なアップデートを行ったほか、排気量を2.9リットルに拡大した「B28E」エンジンを搭載。最高出力は14hpアップの155hpとなりました。さらにゴールド/ヌガーによる新ツートンカラーも採用しました。
最終モデルの年間目標生産台数は800台で、需要はきわめて低く見込まれていました。しかし、実際の生産台数は予想の2倍を超える結果に。
1981年に最終ロットの販売が終了したときは、すでにコレクションの対象となっていました。262Cの生産期間は1977年から1981年までのわずか5年。総生産台数は6622台でした。
ボルボに対する世間の認識を改めさせたモデル。それが262C
今から40年前、ボルボに対する世間の認識を覆したモデル、それがボルボ262C。
200シリーズのベーシックモデルに比べて価格が2倍以上だったにもかかわらず、長く伸びたサイドラインと低く抑えられたルーフが織りなす美しいフォルムが人々の心を動かし、予想をはるかに上回る売上げを記録しました。
それを踏まえてボルボ262Cを見ると、改めて262Cの素晴らしさを感じられますね。