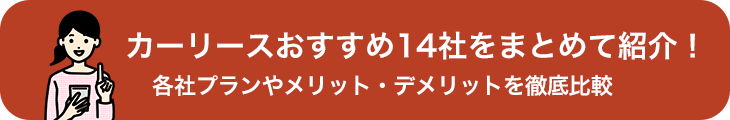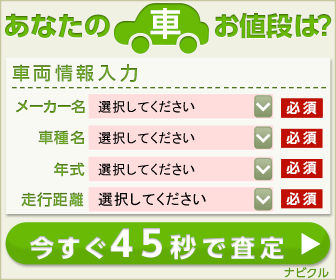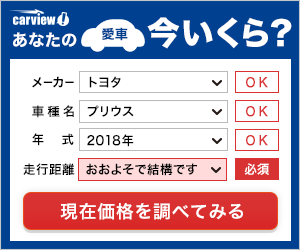オールシーズンタイヤってなに?
《画像提供:Response 》Vector 4seasons Hybrid(ベクター フォーシーズンズ)
オールシーズンタイヤとは、いったいどんなタイヤなのでしょうか。
オールシーズンの名の通り、春夏秋冬どんな季節、天気にも対応した全天候型のタイヤです。
そんなタイヤがあったの!?と驚きました?雪が降ったら専用タイヤと交換が必要だと思っている方も多いと思います。
「うちは狭くてタイヤの保管場所がないよ…」「たまにしか降らない雪のために専用タイヤの購入は家計に響くなぁ…」と悩んでいる方には救世主登場です。
オールシーズンタイヤは、突然の雪でも走行可能で、シャーベット状の路面も心配なし。降雪地域にお住まいの方は別ですが、年に数回雪が降る程度の地域であれば問題ないでしょう。
オールシーズンタイヤのメリットとデメリット
《画像提供:Response 》Vector 4Seasonsを装着したプリウス
オールシーズンタイヤのメリットとデメリットを紹介します。
■メリット1:履き替え不要
オールシーズンタイヤの一番のメリットは、タイヤの履き替えがいらないこと。普段ノーマルタイヤを履いている場合、年に2回のタイヤ交換が必須で、交換費用は、1回5,000円前後です。冬用タイヤの購入も考えるとかなりの出費になります。
ノーマルタイヤの時に、降雪があったら身動きがとれなくなります。それが山道や高速道路を走行中だったとしたら…、想像するだけで怖いですよね。そんな時、オールシーズンタイヤを履いていれば、雪が強くなる前に自宅に帰れたり、一般道に下りてホテルを探すこともできます。
■メリット2:タイヤの保管が不要
タイヤの保管がいらないのは、とても魅力的ではありませんか?タイヤ4本を保管するには、それなりのスペースが必要になります。保管スペースがなくてトランクルームを借りたり、ショップに預かってもらっても費用はかかるので、タイヤの保管が不要だと家計も助かります。
■デメリット1:冬の路面に強くない
履き替えいらず、保管も不要のオールシーズンタイヤのデメリットとして最初に知ってもらいたいのは、冬の路面に強いわけではないないこと。ゴムに特別な素材を使っていて冬でも硬くならず、突然の雪やシャーベット状、圧雪路面にも対応できる全天候型タイヤではありますが、慎重な運転は必須。
軽微な雪道にはもってこいですが、アイスバーン(凍結路面)や深い雪には向きません。雪の状況によっては、チェーンの装着や冬用タイヤへの交換が必要です。
■デメリット2:燃費性能が下がる
オールシーズンタイヤの燃費性能が下がるのは、なぜなのか解説しましょう。1年中履いたままなので、燃費の問題はスルーできませんよね。
オールシーズンタイヤはゴム素材がやわらかいため、転がり抵抗が増えることが原因といわれています。転がり抵抗とは、丸い物が転がる時、進行方向と逆に生じる抵抗力の事で、そこに無理がかかることが、燃費が下がる理由です。
オールシーズンタイヤの交換時期は?

オールシーズンタイヤの交換時期は?
さすがのオールシーズンタイヤでも、ずっと同じタイヤのままでは危険です。交換時期は、基本的にノーマルタイヤと大差なく、目安としては使い始めて3〜5年ほど。使用頻度にもよるので、車をあまり使わない場合も、サービスステーションで確認してもらうと安心です。
交換時期の見極め方

交換時期の見極め方は?
交換時期の見極め方として、タイヤの減り方も確認してみましょう。
タイヤに細かい亀裂があることはもちろん、タイヤのプラットフォームが出たら冬の使用はNG、スリップサインが出たらすべてのシーズンで使用NGで、交換時期が来たと思ってください。不安な時はサービスステーションやショップを訪ねるのもいいですね。
雪道の運転で注意すべきこと

雪道の運転で注意すべきことは?
雪道の運転は、雪国の人でも怖いと聞きます。では、どんなことに注意して運転すべきでしょうか。
まず雪道=滑る!と思っていてください。ほんの少しの雪だからとか、オールシーズンタイヤを履いているから、といって過信は禁物です。気温が低いと路面はすぐに凍結します。普段よりかなり低速で、かつ慎重に走るようにしてください。また、雪の降り方が急に強くなる可能性もあるので、チェーンの準備はしておきましょう。
■急な操作をしない
雪道の運転で急な操作をしてはいけないのは、基本中の基本。急いでいると、信号が青になった途端アクセルを踏み込んだり、急な車線変更や、赤信号に気付くのが遅れて急ブレーキをかけて止まったり、誰でもひとつくらいは経験があると思います。
これらの、急な操作は雪道では絶対にダメ。滑ってしまいハンドル操作もできなくなります。雪道では、普段より車間距離も十分とって走行してくださいね。
発進時のアクセルはゆっくりと踏み、停車時はできるだけエンジンブレーキを使い、ブレーキペダルも優しく踏んで停車してください。
■ホワイトアウト時はハザードを
ホワイトアウトが発生した時はハザードとヘッドランプを点けて、ゆっくりと減速し、他の車に存在を知らせながら停車してください。前後左右真っ白で視界はゼロです。そのまま、ホワイトアウトが落ち着くのを待ちましょう。
■雪でマフラーを塞がない
もし立ち往生してしまったら、雪でマフラーが塞がらないように注意してください。マフラーが塞がると、排気ガスが車内に入り一酸化炭素中毒の危険性があります。吹雪の中での停車は、あっという間に車が雪で覆われてしまいます。救援が来るまでの間、マフラー周りの雪は除雪してください。
■事前にガソリンは満タンにしておく
冬の時期、とくに降雪予報がある時には、事前にガソリンを満タンにしておくのがベストです。すぐに済む用事だからと出かけてしまい、予期せぬトラブルに遭遇してしまうことも考えられます。
例えば、トラックが立ち往生して道をふさいでしまい、積み荷も散乱して動けなくなったとします。エンジンをかけたまま暖房をつけて止まっていても、ガソリンは消費します。この状況でガソリンがなくなりそうになったら、ハラハラしますよね。こんなことにならないように、ガソリン残量のチェックは、お出かけ前にぜひ心がけておいてほしいです。
オールシーズンタイヤを使ってみよう
《画像提供:Response 》ヨコハマタイヤ BluEarth-4S AW21
どうでしたか?便利なオールシーズンタイヤを使ってみようと思いませんか?
タイヤを2セット購入する費用、タイヤ交換費用、タイヤ保管場所の確保費用を抑えられるのは、なかなかのメリットです。最近は、雪道でもよりよく走れて、燃費を抑えたオールシーズンタイヤのラインアップもあるようです。ぜひこの機会に、オールシーズンタイヤを使ってみましょう。