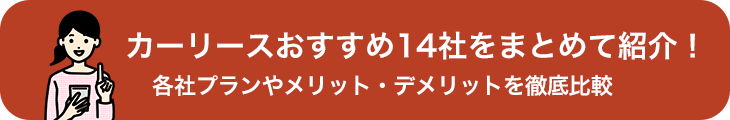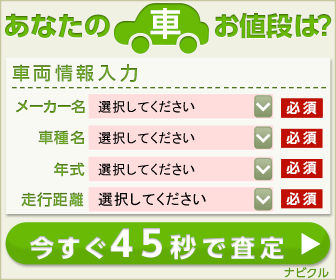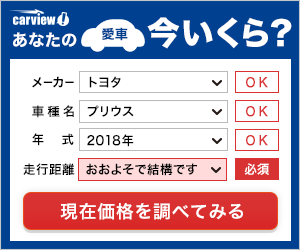走行税とは

走行税って何?
走行税とは、「車が走った距離に応じて課税される税金」のことです。現在は排気量によって支払う自動車税が細かく定められていますが、その税金を走行税という変動制の税制に切り替えようという法改正案が与党内で持ち上がったことにより話題となりました。
採択された場合の具体的な金額は現段階では決まっていませんが、ディーゼル車などに対して道路利用者課金制度を導入しているニュージーランドを参考にすると、最安でも「日本円で1,000kmあたり5,600円」となっています。車両の種類によって負担額が細かく設定されているのですが、最安クラスでも1年間に1万km走った場合は50,000円の負担となるため、走れば走るほど税負担が重くなる制度と言えるでしょう。
ほとんど車を利用しないのであれば税金が安くなる可能性もありますが、日頃から通勤や買い物に利用していたり、バスやタクシー、運送などの交通サービスを担っていたりする方にとっては大幅な負担増につながる可能性があります。
走行税が検討されている理由

走行税はどうして検討されている?
現行の自動車税は所有している自動車に対してかかりますが、日本国内では車の販売台数がこの数年横ばいの状態であり、人口の減少も続くとみられることから、税収もこれ以上大幅な増加が見込めない状況にあります。「若者の車離れ」とも言われるように、若い世代が車を所有することにこだわらなくなり、車を持たずに生活する人は今やめずらしくありません。
また、カーシェアサービスやレンタカーが普及したため、気軽に車を借りられるようになったのも自家用車を持たなくなった一因です。所有しなければ毎年の税金は発生しないため、自然と自動車税の減収につながります。さらに、電気自動車やハイブリッドカーなどの「エコカー」と呼ばれる車に乗る人が増加し、免税・減税措置を受けたり、ガソリン車の比率が低下したりしたことも、税収の落ち込みに拍車をかけています。
複合的な要因によって自動車税の税収が減少に向かっていることが、走行税の導入が議論されるようになった大きな理由です。
走行税のメリット

メリットは?
ここでは、走行税を導入するとどのようなメリットがあるのかについて解説します。
■あまり乗らない人は税金が安くなる可能性がある
車を所有しているものの、ほとんど乗らないという人も中にはいるでしょう。その場合は、現行の固定で料金が定められている自動車税に比べて支払う税金が安くなる可能性もあります。
交通網の発達した都市圏や市街地では、公共交通機関を使えれば十分に生活できるという方も少なくないため、自動車税の負担を考えて車を手放すかどうか検討するケースもあるでしょう。
走行税の導入で走った分だけの税金を徴収される形式に制度が改まれば、「乗らなくても持ち続ける」選択肢を選びやすくなると考えられます。
■電気自動車やハイブリッドも一律で徴収できる
現行の制度では、ハイブリッドカーや電気自動車などのエコカーは自動車税が優遇されているため、直接的な税収の減収につながっています。
また、ガソリンを使わない仕様も減少要因のひとつです。走行税を導入することにより、ガソリン車とエコカーの徴収基準を揃えられるため、免税・減税対象だった車にも税金を発生させることが可能になります。
走行税のデメリット

デメリットについても知っておこう
いくつかのメリットがある一方で、走行税のデメリットは非常に多いと言われています。ここでは、走行税導入のデメリットを紹介します。
■支払う税金が増える
日本の自動車税は、すでに複数種類の税金がかけられているため、走行税が増えるとさらに支払う税金が増える可能性が高まります。遠方に車で外出する機会が頻繁にあったり、通勤などで日常的に使用しており年間の走行距離が多かったりする場合は負担が激増するでしょう。
一般的な1年間の走行距離は、近所のスーパーの買い物に時々使用する程度で5,000km未満、買い物以外に休日のレジャーにも使用する場合で5,000km~10,000km、日々の通勤やレジャーをはじめ、帰省などの長距離運転もする場合で10,000km以上と言われています。
年間走行距離の平均は7,000km程度とされており、たとえば1kmあたり5円の走行税が導入された場合は、1年間で35,000円の走行税を支払うことになります。軽自動車税が10,800円であることを考えると、実に24,200円もの負担増です。
15,000kmになると75,000円にも跳ね上がるため、一般的な普通車の自動車税も大きく上回るケースが多くなるでしょう。
■正確な走行距離の申告方法が整備されていない
1年間にどのくらいの距離を走ったのか正確に申告する手段が確立されていないため、不平等な徴収になるリスクがあります。GPSを利用して走行距離を計測し、その結果をもとに税額を決定する案もありますが、プライバシーの侵害にあたる可能性があるため導入のハードルは高いと言えます。
公平性を保った徴収方法を決められなければ、導入の議論は前に進まない可能性が高いです。
■地方在住者の負担の比重が大きくなる
地方在住者にとっては、車が唯一の移動手段という場合も少なくありません。日常的に車を利用しなければならない環境であれば、必然的に走行税の負担は大きくなります。
公共交通機関に切り替える手段を講じられる都市圏在住者とは異なり、「強制的に増税になる」という印象を受ける人も多いでしょう。
■配送料などの値上げにつながる
長距離トラックなどを数多く抱える運送業者や、走行距離の長いバスやトラックなどの交通サービスを運営する企業にとっては、ランニングコストの大幅な増加につながります。
企業努力でカバーしきれないコストについては、サービス料の値上げなどによって消費者の負担になる可能性も高いです。
■車離れに拍車をかける
車を持たない若年層が増えていると言われて長い年月が経ちますが、走行税の導入はさらに車離れに拍車をかける要因になります。
税収を増やす目的で導入されても、車に乗る人が大幅に減ると結果的に減収となってしまうリスクも考えられます。
世界では走行税が導入されている国もある

走行税が導入されているのは?
世界には、すでに走行距離に応じた課税制度が導入されている国もあります。ニュージーランド、アメリカ、ドイツの例を見てみましょう。
■ニュージーランド
ニュージーランドは世界でも比較的早い段階で走行税の導入に踏み切りました。
課税対象の車種はディーゼル車などで、走行予定の距離を事前に1,000km単位で申告して納税するシステムが採用されています。(申請時より走行距離が増えた場合は再申請が必要)
金額は約90種類にも細分化されており、マイクロバスで1,000kmあたり5,000円程度に設定されています。
■アメリカ
アメリカ全土で導入されているわけではありませんが、オレゴン州では有志の自由参加のもとで導入されており、他にもカリフォルニア州をはじめとした複数の州での実証実験も行われています。
世界では税収を増加させる目的だけではなく、化石燃料の使用を抑制するための税金として注目されている側面も大きいと言えます。
■ドイツ
ドイツにおいては、12トンを超える大型トラックに対して走行税が定められています。計測用の車載器の搭載が義務付けられており、車載機が計測した走行距離とCO2の排出量に応じて税額が決定される仕組みです。
ドイツでは陸上交通が発達していますが、大型トラックが原因の渋滞が社会問題となっています。走行税が導入された背景には、混雑緩和のねらいも含まれています。
走行税の導入時期は現在のところ未定

日本国内で最初に走行税の導入が議論され始めたのは2018年のことですが、2019年度・2020年度の税制改正大綱ではともに採択が見送られています。「課税については中期的な視点に立って行う」という見解に基づき、導入には慎重な姿勢を示しています。そのため、今後の導入時期は現在のところ未定であり、具体的な動きがいつになるかも判然としないのが現状です。
とはいえ、自動車税の減収は今後も続いていくとみられており、何らかの対策を講じたい政府が導入を急ぐ可能性も否定できません。導入される可能性も見据えて、知識を身に付けておくことが大切です。