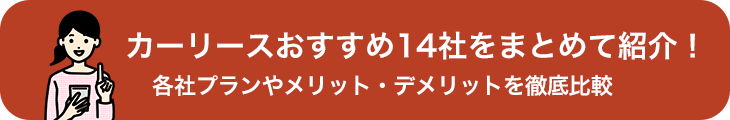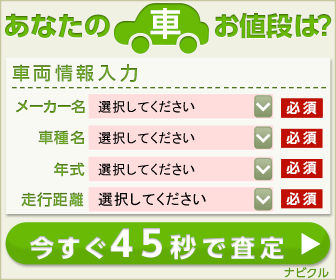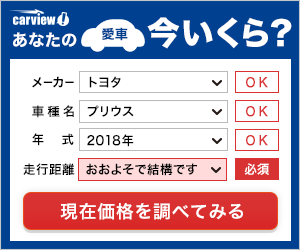なぜ東名高速は「E1」と呼ばれるのか

東名高速道路
首都圏と関西圏を結ぶ国道1号線沿いを走り、東京から名古屋間を繋ぐ高速道路と位置付けられている東名高速。その東名高速は、高速道路表記のナンバリング化により「E1」とも表記されるようになりました。
従来の地名にちなんだ路線名に加えて、数字とアルファベットの組み合わせによる名称も併用されているわけです。「E1」は、高速道路を意味する英単語「Expressway」の頭文字「E」に、並行する国道1号線の「1」を組み合わせた呼称となります。
高速道路ナンバリング

高速道路ナンバリング
なぜ、東名高速を「E1」で表すような、高速道路のナンバリング化が導入されたのでしょうか?その答えとしては、日本の国際化に向けた取り組みの一つであるためと言えるでしょう。
地名に依存せず、国際標準とも言える数字とアルファベットによる簡易な名称を用いることにより、日本語に不慣れな来日ドライバーにも分かりやすい表記を目指しているというわけです。
2010年代に入り、日本を訪れる外国人の数が増加する傾向にあります。国土交通省によると、2011年から2015年にかけて訪日外国人の数は3.2倍に増加したとされています。加えて2011年から2013年までの3年間で外国人のレンタカー利用も2.8倍増え、約50万人に達しました。
訪日外国人の増加に伴い、その方々が日本で自動車を運転するケースも増えているというわけです。そのような背景に基づき、2017年から、国際的にも通用する高速道路のナンバリング運用が開始されるに至りました。
■路線番号とは

国道標記
そもそも路線番号とは、道路の路線に割り当てられた番号のことを意味します。国道1号線などの名称に見られる数字がそれに該当するわけです。
一般道、すなわち国道および地方道について、路線番号は基本的に数字で表されます。道路標識では、いずれも青地に白地で番号を記す形式が取られています。標識の形状が国道では逆三角形、地方道では六角形となっており、これにより国道と地方道の区別が付けられているわけです。
高速道路ナンバリング導入以前の日本では、一般国道、都道府県道や市町村道といった地方道、首都高速・阪神高速・名古屋高速などの都市高速において路線番号を用いるのが主でした。
しかし、都道府県をまたぐ都市間高速道路には路線番号がなかったわけです。これは世界的には珍しい日本特有とも言える状態でした。
海外では、高速道路にも路線番号を用いるのが一般的です。つまりその国の言語を知らなくとも内容を理解できるような標識が、高速道路の路線把握に利用されているわけです。そのような在り方が世界標準となっていると言って差し支えありません。
日本の場合、周囲を海に囲まれた島国という地理的特徴があります。外国人が車道から国境を通過し国内外を行き来することがありません。そういった関係上、日本国内の道路を走行するドライバーは日本人が大多数であり、日本語地名に基づく高速道路表示のみでもさして問題はありませんでした。
しかし、国際化に伴う外国人ドライバーの増加という時代の流れに即し、世界標準に併せる必要性が生じてきたわけです。
■路線番号の付け方
ナンバリングが導入された高速道路も含めて、道路の路線番号はどのような決め方で付けられているのか、見ていきたいと思います。
地方道すなわち都道府県道や市町村道では、その道路を管轄する地方自治体によって何号線とするか決定されます。互いの番号が重複するなどして混乱をきたさないよう、自治体各々の判断に基づき定められるものと言えるでしょう。
日本全国を結ぶ大動脈的な役割を担うものとして整備されてきた国道は、1952年の新道路法改正によって、1級国道と2級国道に分類されました。1級国道としては1号線から58号線までの1桁ないし2桁までの番号を用い、2級国道は3桁の番号を当てるものと定められたわけです。
その後、国道の1級ないし2級の区分は1964年の法改正により廃止され、現在の一般国道となりました。しかし国道の路線番号についてはそのまま継承され現在に至ります。
高速道路の路線番号は、その国道番号を一部流用し、ナンバリングの基本的ルールに従って付けられます。
その基本ルールとしては、主に以下のものが挙げられます。
◆地域に馴染みがあり親しみやすい旧1級国道の番号を使用。
◆数字は原則2桁。
◆起終点が同一など、機能的に似ている路線はグループ化。
◆道路種別や機能をアルファベットで表現。
◆国土の骨格構造が表現できるよう設定。
その基本ルールに則って定められた具体的ルールは、以下の通りです。
1):1桁ないし2桁の旧1級国道に並行する路線は、高速道路を意味する「E」に国道番号を付けます。東名高速「E1」はその代表例と言えます。
2):1)に該当する高速道路が存在し、それと機能的に類似している路線は、末尾にグループ化を意味する「A」を付けます。例としては、東名高速「E1」とほぼ並行している新東名高速「E1A」が挙げられます。
3):首都圏などの環状道路は、「E」に代わって円を意味する英単語「circle」の頭文字「C」を用います。C以下の番号については、都市高速との整合性を加味して考慮されます。必ずしも番号が用いられるとは限らず、東京湾アクアライン「CA」のようにアルファベットが用いられる場合もあります。
4):1桁ないし2l桁の番号を持つ国道に並行する路線の対象を拡大して付番する場合もあります。
3桁番号の旧2級国道と並行する場合、並行している国道番号が別路線に付番されている場合、隣接して2桁国道があれば、該当する国道番号を延伸して用います。
また、北海道縦貫自動車道については、国土の骨格構造を表す路線であることから、全線を「E5」と付番しています。
5):1)~4)に該当しないその他の高速道路については、国道番号に使用されていない59番以降の2桁を用います。
■主な道路の路線番号
主な高速道路の番号はどのように付けられているのか、ナンバリングのルールの実例として確認しながら見ていきたいと思います。
名古屋から神戸間を結ぶ高速路線に位置付けられる名神高速。これは、国道1号線に並行する路線として、東名高速と同じく「E1」が用いられています。
その名神高速と機能的に類似している路線である新名神高速道路は、E1をグループ化したものと見做され、「E1A」となるわけです。
愛知県と富山県を結ぶ東海北陸自動車道は、2桁国道である国道41号線と方向的に類似していることから「E41」となります。
函館・江差自動車道は「E59」とされています。グループ化や対象拡大などの関連付けが既存の国道と取れないため、国道の2桁番号に用いられていない59以後の番号が当てられます。
■路線番号は浸透している?
世界的に広く用いられている高速道路の路線番号は、上位路線に1桁や2桁の数字を振り、並行路線や枝に相当する路線は桁を増やしていくという方法で番号が決められています。
しかし日本の場合、主に国道番号に準じて付番されているため、番号間の法則性がほとんど見られません。
例えば、大分自動車道E34の次番に当たるE35は、大分から遠く離れた北海道横断自動車道根室線を指すという状態です。
そのような馴染みにくさもあり、導入して間もない現時点では高速道路の路線番号が浸透しているとは言い難い状況にあります。
しかし、ドライバーにとって高速以上に利用頻度が高い一般国道と関連付けられていることもあり、導入から年月が経過するにつれ徐々に慣れてくるものと思われます。
■路線番号が付けられる道路は?
高速道路ナンバリング化により、従来の国道、都道府県道、市町村道に合わせて高速道路についても路線番号が付けられることになりました。
このことから、今後は路線番号が付けられる道路は主な車道全般が該当すると言えるでしょう。
まとめ

東名高速道路
東名高速がE1と表記されるのを起点に、高速道路の路線番号について紹介してみました。導入されて年月的に浅く、未だ馴染みの薄い印象を持たれますが、外国人ドライバーの増加など国際化に対応する上で今後重要性を増してくるでしょう。