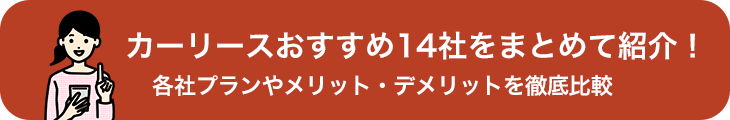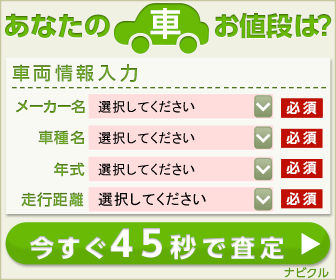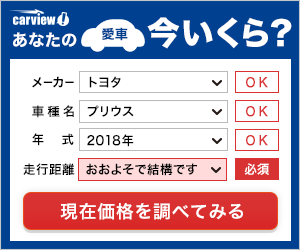Japan Mobility Show 2025とは?
《画像提供:Response》《画像提供 自工会》 ジャパンモビリティショー2025の企画概要
Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー)は、70年の歴史を持つ「東京モーターショー」から進化したモビリティ総合イベントです。テーマは「ワクワクする未来を、探しに行こう!」。
自動車の展示にとどまらず、未来の暮らしや文化、ビジネスまでを包括的に体験できるのが特徴です。会場は「モビリティの未来(#FUTURE)」「モビリティ文化(#CULTURE)」「モビリティのビジネス(#CREATION)」という3つの柱で構成され、来場者は次世代のモビリティを「見て・触れて・楽しむ」ことができます。
Japan Mobility Show 2025 開催概要
《画像提供:Response》《画像提供 自工会》 ジャパンモビリティショー2025の企画概要
Japan Mobility Show 2025は、2025年10月30日(木)から11月9日(日)までの11日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)で開催されます。会期中はプレスデーやオフィシャルデー、特別招待日を経て、一般公開日が設けられ、多彩なプログラムが展開されます。
出展者は乗用車、商用車、二輪車、車体、部品・機器、モビリティ関連など6カテゴリーにわたり、合計136社(2025年6月24日時点)が参加予定です。チケットは9月上旬から公式ウェブサイトにて販売開始予定で、詳細は順次発表されます。
国内外のメーカーや関連企業が一堂に会し、次世代モビリティの最新動向を直接体感できる絶好の機会となっています。
見どころ① Tokyo Future Tour 2035
《画像提供:Response》《画像提供 自工会》 ジャパンモビリティショー2025の企画概要
Japan Mobility Show 2025注目の見どころが「Tokyo Future Tour 2035」です。2035年の東京を舞台にした未来都市を再現し、来場者は「移動」「暮らし」「社会」がどのように変わっていくのかを体感できます。ここでは、電動化や自動運転技術といった先端モビリティの進化だけでなく、エネルギーや通信インフラ、街づくりまでを含めた未来像が提示されます。
会場は「#FUTURE」「#CULTURE」「#CREATION」という3つの柱に沿って構成され、展示やシミュレーション、体験型コンテンツを通じて、技術と生活の結びつきを実感できる内容となっています。子どもから大人まで楽しめる没入型プログラムとして、多くの来場者が注目するエリアです。
見どころ② モビリティ文化体験 #CULTUREゾーン
《画像提供:Response》《画像提供 自工会》 ジャパンモビリティショー2025の企画概要
「#CULTURE」ゾーンでは、モビリティの持つ文化的な魅力を多角的に体験できます。歴代の名車や二輪車、スーパーカー、キャンピングカーなどが一堂に展示されるほか、デモランや同乗体験が用意され、往年の名車から最新モデルまで走りの魅力を直接味わえるのが特徴です。
さらに、会場外にはキッチンカーが集結するフードエリアが設けられ、来場者は食とクルマ文化を同時に楽しむことができます。単なる展示にとどまらず、「見て・乗って・味わう」体験を通じて、モビリティが社会やライフスタイルに根付いてきた背景を感じられるゾーンです。家族や友人同士で訪れても楽しめる、親しみやすさのあるエリアとなっています。
見どころ③ Startup Future Factory
《画像提供:Response》《画像提供 自工会》 ジャパンモビリティショー2025の企画概要
「Startup Future Factory」は、スタートアップと事業会社が出会い、新たな共創を生み出すためのビジネスゾーンです。会場内では多彩なスタートアップ企業がブースを構え、最新のモビリティ関連技術やサービスを披露します。
さらに、ピッチコンテストやアワードが実施され、革新的なアイデアが広く発信される場となります。来場者は新しい技術を知るだけでなく、実際に企業担当者と交流できる機会も用意されており、ビジネスマッチングの拠点としても注目されています。
また、事前マッチングや商談をサポートする「Meet-up Box」などの仕組みも導入され、効率的にビジネスの可能性を探れる点が大きな特徴です。
見どころ④ Out of KidZania
《画像提供:Response》《画像提供 自工会》 ジャパンモビリティショー2025の企画概要
子ども向けの特別企画として注目されているのが「Out of KidZania」です。職業体験テーマパーク「キッザニア」とのコラボレーションにより、小学生以下の子どもたちがモビリティ関連の仕事を実際に体験できるプログラムが展開されます。
自動車整備士やデザイナー、ドライバーなど、モビリティに関わる職業を模した体験を通じて、子どもたちは楽しみながら学ぶことができます。親子で参加できる内容になっているため、家族連れの来場者にとっても魅力的なコンテンツです。未来の世代がモビリティの世界に関心を持つきっかけとなり、教育的な意義も大きいプログラムとして期待されています。
見どころ⑤ トークセッション
《画像提供:Response》《画像提供 自工会》 ジャパンモビリティショー2025の企画概要
Japan Mobility Show 2025では、モビリティ業界の最前線で活躍する専門家や企業のリーダーが登壇する多彩なトークイベントも予定されています。「未来モビリティ会議」をはじめとするセッションでは、電動化や自動運転、次世代インフラ、グローバルな産業動向といったテーマが議論され、来場者は最新の知見に触れることができます。
さらに、企業によるプレゼンテーションやパネルディスカッションも行われ、技術革新の裏側や社会実装の課題について深く理解できる内容となっています。展示や体験型コンテンツと合わせて、知識を広げ、未来のモビリティ社会を考えるきっかけになるプログラムです。
出展メーカー・注目ブース
《画像提供:Response》《写真提供 ホンダ》 ジャパンモビリティショー2023
Japan Mobility Show 2025には、国内外の主要メーカーが出展し、最新技術や次世代モデルを披露します。なかでも注目されるのがHondaのブースです。四輪の新世代EV「Honda 0(ゼロ)シリーズ」や二輪の次世代モデルに加え、小型ビジネスジェット「HondaJet Elite II」のモックアップなど、空・陸を横断する幅広いモビリティを紹介します。
そのほかトヨタ、日産、三菱、マツダといった国内メーカーや海外ブランドも参加予定で、電動化や自動運転、コネクテッド技術など各社の強みを打ち出す展示が期待されます。最新モデルの展示に加え、体験型デモンストレーションも用意され、来場者は「未来の移動」を多角的に体感できるブースが揃っています。
チケット・参加方法
《画像提供:Response》《画像提供 自工会》 ジャパンモビリティショー2025の企画概要
Japan Mobility Show 2025 のチケット情報は以下の通りです。
・販売時期:チケットは 2025年9月上旬よりオンラインで発売開始されます。会場での当日販売やチケット窓口の設置はありませんので、必ず事前に購入しましょう。
・購入方法:公式サイトや英語版サイトからの購入が可能。コンビニ(セブン-イレブン、ファミリーマートなど)でも取り扱われますが、会場付近では混雑が予想されるため、事前購入がオススメです 。
・料金(税込):
| 入場券(税込) | 当日券 | アフター 4 ※1 | アーリーエントリー ※2 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 3,000円 | 1,500円 | 3,500円 (限定5,000枚/日) |
| 高校生以下 | 無料 | ||
| 小学生以下 | 無料:但し、保護者の同伴が必要 | ||
※1) 一般公開日(月~土曜日)の16:00以降に入場可能。
※2) 一般公開日(土日・祝日)の9:00から入場可能(一般入場は10:00から)。保護者同伴の場合は小学生以下無料。
・高校生以下及び自動車専門学生・高等専門学生は無料。入場時に学生証の提示が必要。
・ 障がい者手帳のある方は、本人と付添1名(車いすの場合は2名まで)が無料。入場時に障がい者手帳の提示が必要。
・「Out of KidZania in Japan Mobility Show 2025 」、「日本自動車ジャーナリスト(AJAJ)と巡るガイドツアー」は、Japan Mobility Show公式アプリにて9月下旬ごろから予約受付を開始予定。
まとめ
《画像提供:Response》《画像提供 自工会》 ジャパンモビリティショー2025の企画概要
Japan Mobility Show 2025は、「東京モーターショー」から進化した新しい形のモビリティ総合イベントです。今回のコンセプトは「ワクワクする未来を、探しに行こう!」。未来の都市体験を再現する「Tokyo Future Tour 2035」、文化としてのクルマやバイクを楽しめる「#CULTURE」ゾーン、スタートアップと企業が出会う「Startup Future Factory」、子ども向けの「Out of KidZania」、そして専門家によるトークセッションなど、多彩なプログラムが用意されています。
大人から子どもまで楽しめるだけでなく、ビジネスや技術革新の現場に触れられる点も大きな魅力です。次世代のモビリティ社会を体感し、未来の可能性を感じ取れる貴重な機会として、ぜひ会場に足を運んでみてください。