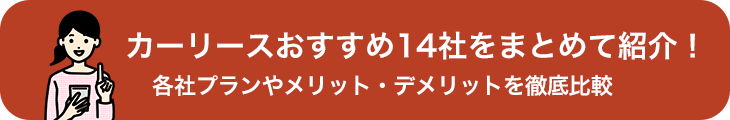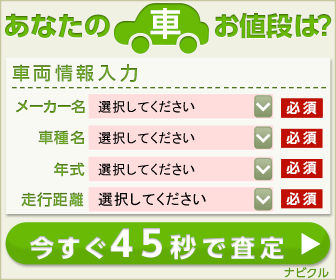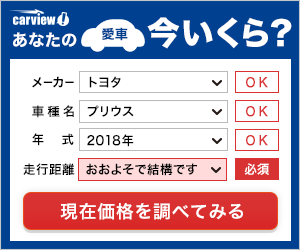中型免許とは?

三菱ふそう・中型トラック ファイター
冒頭でもご紹介しました通り、中型免許は平成19年6月2日の道路交通法改正の際に新設された免許の種類です。それ以前は自動車の免許は普通自動車免許と大型自動車免許の2種類のみで、普通自動車免許でも、現在中型自動車に分類されている一部車両の運転も可能でした。
中型免許新設以前に普通自動車免許を取得した方の中には、かなり大きな車まで運転できることに驚いてしまったという方もいらっしゃるでしょう。これが問題で、普通自動車免許を取得する際の教習や試験においては中型車運転の技能は求められません。そのため、運転は可能でも実際の運転は難しいという問題がありました。
そこで、普通運転免許と大型運転免許の間に中型運転免許が新設されることになったのです。
■どんな車を運転するのに中型免許が必要?
中型運転免許が必要となるのは、その名の通り中型自動車に分類される車両です。車両総重量が7.5t以上11t未満、最大積載量が4.5t以上6.5t未満で、乗車人数が11人以上29人以下のものを指します。
こう言ってしまうと、少し難しく感じられるかもしれませんが、もっともイメージしやすいのは4tトラックと呼ばれる車両です。このサイズのトラックが運転できれば中長距離の運送業務なども可能となります。また、乗車人数が11人以上29人以下なのでマイクロバスの運転も可能です。
一般的に自家用車として使用される普通自動車が中型以上のサイズになることはほとんどありませんが、運送業などの業務を行う場合は中型免許が必要となるケースが多くなります。
中型免許ができる前に普通自動車免許を取得していた場合は?
前述の通り、中型免許が新設されたのは平成19年6月2日です。では、それ以前に普通自動車免許を取得していた場合はどうなるのか気になるという方も多いでしょう。
中型免許新設前に普通自動車免許を取得していた場合、すべての中型自動車が運転できるわけではありませんが、以前と同様に車両総重量8t未満、最大積載量5t未満までの車両の運転は可能となっています。
そのため、この範囲であれば新たに中型免許を取得することなく運転することができます。この免許は現在の中型免許と区別するために「8t限定中型免許」と呼ばれています。つまり、平成19年6月以前に取得している場合は普通自動車免許で4tトラックは運転可能であるということになります。
■準中型免許との違いは?
現在では普通・中型・大型以外にももうひとつのカテゴリーが追加されています。それが平成29年3月12日に新設された準中型免許です。
準中型免許で運転できるのは、車両総重量が7.5t未満、最大積載量が4.5t未満、乗車定員が10人以下の車両となっています。
中型免許をさらに細かく分類したという形になります。
詳しくは後述しますが、中型免許は20歳以上、運転経験2年以上といった条件を満たさなければ取得することができません。しかし、普通自動車免許で運転できる車の制限が厳しくなったことから、高校を卒業してすぐに運送業などに従事することが難しくなってしまいました。
こういった問題を解消するために、18歳から取得できる準中型免許が新設される形になりました。
中型免許取得の方法は?

どうやって取得する?
中型免許を取得することによって、運転できる車両の幅はかなり広くなりました。自家用の普通車を運転するのみであれば、普通自動車免許でもほぼ問題はありませんが、運送業などに従事するのであれば中型免許が必須となるケースもあります。
そこで、中型免許の取得を検討している方も多いでしょう。続いては中型免許を取得する方法について詳しくご紹介します。
■中型免許取得に必要な資格はある?何歳から取得できる?
普通自動車免許と準中型自動車免許は18歳から受験資格を得ることができます。しかし、中型免許は20歳以上でなおかつ運転経験2年以上という条件を満たさなければ取得することができません。
運転経験が必要なことからもわかる通り、中型免許を取得するためには普通自動車免許などを取得している必要があります。
■中型免許はどうやって取得する?
中型免許取得の方法としてもっとも一般的なのは教習所に通うという方法です。一発試験での取得も可能ではありますが、かなりハードルが高く、中型車両の運転経験がない方が合格するのはかなり難しいと言えます。
そのため、教習所を卒業してから適性試験を受けて取得するという形が一般的です。
■取得までにかかる期間や費用
中型免許の取得にかかる期間は普通自動車免許を所持している場合で1~2ヶ月、8t限定中型免許や準中型免許を所持している場合で3週間~1ヶ月程度が目安です。教習所の混雑具合によってはさらに時間がかかるケースがありますので、スケジュールには余裕を持っておきましょう。
費用は普通自動車免許を所持している場合は17~25万円が相場です。8t限定免許や準中型免許を所持している場合は14~20万円が相場となっています。
費用については教習所によってバラつきがありますので、事前に確認しておくようにしましょう。また、合宿免許などを利用すればより短期間かつ低料金で取得できるケースもあります。より早く免許を取得したいという方は確認してみましょう。
また、教習所によって取得することのできる免許は異なっていますので、必ず中型免許に対応したところを事前に確認した上で選ぶようにしましょう。
■中型免許取得までの流れ
中型免許取得の流れは基本的に普通自動車免許とそれほど大きな違いはありません。まずは教習所に入校してから教習を受けることになります。期間は先ほどご紹介しました通り1~2ヶ月程度です。
教習所で卒業試験に合格し、卒業すれば管轄の試験場で適性試験を受け、合格すれば中型免許取得となります。
中型自動車は普通自動車よりもかなりサイズが大きく、感覚もまるで違っていますので、取得までに時間がかかってしまうというケースも少なくありません。なので、仕事などで中型免許が必要となる場合は、できるだけスケジュールに余裕を持っておくことをおすすめします。
まとめ

中型免許を取ろう!
中型免許が新設されたことによって、普通自動車免許では4tサイズのトラックなどを運転することができなくなりました。そのため、運送業などに従事する場合は中型免許を取得しなければならなくなっています。
そのため、中型免許の取得を考えている方も多いでしょう。現在では、中型以外にも準中型免許という選択肢もありますので、自分が運転したい車のサイズなどを確認した上でどの免許が必要なのかを考えるようにしましょう。