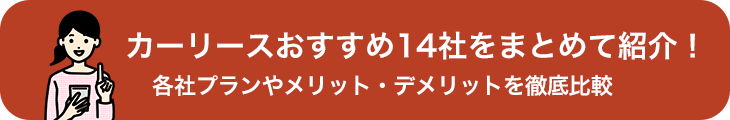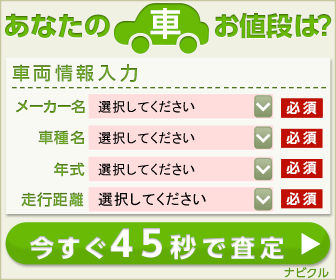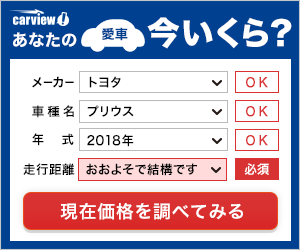仮免学科試験とは
自動車教習所で自動車免許を取得するためには、仮免許試験に合格した上で本免許試験にも合格しなければなりません。仮免許試験は学科試験と技能試験から構成されており、仮免許試験の学科試験を仮免学科試験と呼びます。
仮免学科試験は、路上で自動車運転を行うにあたって必要な知識を身につけられたかどうか確かめるために行われます。そのため、仮免学科試験で問われる内容は交通ルールや自動車運転に関する基本的な事項ばかりです。
仮免学科試験では、試験時間30分で50問が出題されます。

出題範囲は第1段階の学科教習で習ったことで、すべて〇×式で出題されます。各問2点で、全50問の90%である45問以上の正解で、仮免学科試験に合格できます。
仮免学科試験の問題は、AT限定免許とMT免許、自動二輪免許で共通しており、すべて同じ問題です。
仮免学科試験が不合格になっても、特にペナルティはありません。受ける意思がある限り、何度でも受験できます。ただ、仮免学科試験に合格しなければ仮免許も取得できず、第2段階には進めません。
試験に合格できずにいると、必然的に教習所の在籍期間が長くなります。教習全体の有効期限は最初に教習を受けた日(技能だけを受ける場合は技能教習の初回受講日)から9ヶ月と決められているので注意が必要です。
仮免学科試験は毎日あるわけではないので、1回1回を大切にしていきましょう。
また、多くの自動車教習所では仮免学科試験の再受験には、再受験料を設けています。再受験料の多くは2,000円~3,000円程で、再受験の度に所定の金額を支払わなければいけません。なお、仮免学科試験の合格率はおよそ9割といわれています。
仮免学科試験ではまぎらわしい言い回しやひっかけ問題が多いため、コツがつかめないと合格も難しくなります。
仮免学科試験では記憶力や読解力も問われますが、何より慣れが重要なので、数回落ちたくらいは気にしないでください。筆者の知人にも、仮免学科試験に6回落第した人がいますが、免許取得後はずっと無事故無違反です。仮免学科試験の成績が悪かったからといって、「運転に不向きだ」と落ち込む必要はありません。
■仮免学科試験を受ける場所はどこ?
仮免許の学科試験は公安委員会が指定する自動車教習所で受ける方法と、各都道府県の運転免許試験場もしくは、運転免許センターで直接受験する方法があります。
自動車教習所の場合、通っている教習所のみでの受講となり、他の自動車教習所で仮免許の学科試験だけを受験することはできません。
各都道府県の運転免許試験場もしくは、運転免許センターで受験する人は、一発合格を目指す人が多いため、はじめて仮免許の学科試験を受ける場合は、通っている教習所で受験するのが望ましいでしょう。
仮免許の学科試験は即日結果がわかるので、合格すればすぐに技能試験の申し込みができます。
運転免許試験場もしくは運転免許センターは、各都道府県に1か所~4か所ほどしかありません。遠方になるので移動時間もかかります。
普段慣れた場所で確実に合格したい人は、通っている教習所での受験がおすすめですし、教習所に通わず一発合格を目指す人は、運転免許センターか運転免許試験場での受験です。
■本免許試験を受ける場所はどこ?
本試験は、自動車教習所ではなく、住民票の登録している自治体を管轄している運転免許試験場、もしくは免許センターで受験します。住民票がある地域になりますので、住民票がどこに登録してあるか確認が必要です。
受験から合格までの流れは以下のようになります。
・住民票が登録してある場所を確認する
・住民票のある自治体が管轄する運転免許試験場または免許センターをチェックする
・試験時間を確認する
・必要書類を準備する
・運転免許申請書
・卒業証明書
・本籍記載の住民票
・本人確認書類
・申請用写真
・手数料:3,800円(AT・MT問わず同一料金)
自宅から遠い場合、事前にルートを調べて余裕をもって出かけるようにします。また、手数料は、AT・MTに限らず一律3,800円ですが、電子マネーなどに対応していない場合もあるので、必ず現金を持っていくようにしましょう。
本免許試験と同じ内容?
仮免学科試験と本免許試験では、いくつか異なる部分があります。主な異なる点は出題数と出題範囲、試験時間です。
出題数は、仮免学科試験が文章問題50問なのに対し、本免許試験では文章問題90問の他、イラスト形式の危険予測問題が5問の計95問が出題されます。危険予測問題では、出題されたイラストを見てドライバーとしてどのような危険に備えればいいかを答えます。
仮免学科試験の出題範囲は第1段階の内容のみですが、本免許試験では、試験までに習った第1段階および第2段階すべての内容から出題されます。もちろん、仮免学科試験の出題範囲も本免許学科試験の出題範囲に含まれます。
試験時間は仮免学科試験が30分、本免許試験は50分です。
本免許試験も仮免学科試験と同じく90%以上の正解で合格となります。本免許試験の配点は90問ある文章問題がそれぞれ1点、5問ある危険予測問題がそれぞれ2点で、合計100点です。
仮免学科試験ではどんな問題がでる?
仮免学科試験では自動車運転の基礎的な部分が問われます。
例えば、合図の時期、標識・標示の意味、信号の意味、追い越しの可否、優先道路、一般常識、自動車や二輪車の免許制度などについてです。
特に、道路交通法の内容を取り上げ、交通ルールを正確に理解していないと解けない問題が多いのが特徴的です。これらの基礎的な知識は免許取得後に公道を走るときにも必須になるので、しっかり身につけておきましょう。
実際に仮免学科試験の予想問題を複数回こなせばわかるとおり、出題される所はある程度決まっていて、まぎらわしい部分や自動車運転に必要な知識は頻出します。
例えば、普通車や大型車の法定速度は60km/hであるのに対し、原動機付自転車は時速30km/hが法定速度として定められています。
この規則が試験問題に出るなら、「普通車や大型車の法定速度は60km/hであるのに対し、原動機付自転車の法定速度は時速40km/hである」というかたちで出るかもしれません。
多くの人が間違えやすいところでは、以下の分野が挙げられます。
・ 二輪車の二人乗りが許可される条件
・信号の意味(手信号、黄の点滅、赤の点滅信号を含む)
・停止線が無いところの停止位置
・まぎらわしい標識(駐車禁止と駐停車禁止、追い越し禁止と追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止など)
・緊急自動車の優先
・車両けん引時のルール
・二段階右折
・追い越し
・免許で運転できる車の総重量
これらの他にもよく問われる部分は多く、練習問題でも繰り返し出題されています。何度か問題をこなすうちに出やすい分野が次第に分かってくるでしょう。
出題される範囲では、交通ルールの他に一般常識という分野があり、例えば「運転中にタバコの吸殻を窓から投げ捨ててもよい」「道路の真ん中に寝転がってはならない」というような、一般常識を問うものです。
こうした一般常識の問題は、特に試験勉強をしていなくても正答できるものばかりなので、得点源になります。取りこぼさないように、問題文をよく読みましょう。
その他に注意したいのは、ひっかけ問題です。ひっかけ問題は、感覚的に答えてしまうと間違える場合が多いため、やはり問題文をよく読むのが重要です。
例えば、過去に出題されたことのある「赤信号では必ず停車しなければならない」という問題。
一般的な感覚では、つい〇をつけたくなってしまいますが、正解は×。その理由は、緊急車両には赤信号での停止義務がないからです。このように少し意地悪な問題が出題されることもあるため、注意しましょう。
こうしたひっかけ問題への対策は、問題を多くこなして、できるだけ多くのひっかけ問題を経験しておくのがおすすめです。
あわせて、「必ず」「すべての」「しなければならない」といった表現に警戒することが有効です。 これらの表現が出てくる問題文では、「~という例外がある」という答えを設けて回答者を間違えさせようとしている場合が非常に多いからです。
なお、自動車教習所の学科試験は都道府県ごとに作成されるため、その都道府県の状況に合わせた問題が作られます。
例えば、積雪の多い地域では路面凍結についての問題が入れられたり、東京や大阪などの都市圏では交差点のルールについての出題が多くなる傾向があります。ただし、難易度の差が都道府県ごとに出ないよう配慮されているため、どこの都道府県で受けても難易度は変わりません。

仮免学科試験は独特の形式を持つテストなので、どう勉強すればいいかわからないかもしれません。ひと昔前は市販のテキストで勉強するくらいしかありませんでしたが、現在ではさまざまな方法で勉強できます。
おすすめなのは、試験問題集のスマートフォンアプリ。仮免学科試験は〇×問題なので簡単な操作で回答でき、スマートフォンと非常に相性がいいので、通学・通勤時などのちょっとしたすき間時間にも効率良く勉強ができます。試験問題集アプリの中には無料で公開されているものも多く、中には標識だけなど特定の分野のみを扱ったアプリもあります。
あるいは、全国の教習所が公開している試験問題集を活用してみてもいいでしょう。
京都府の宝池自動車教習所や宮崎県の西都自動車学校など、試験問題集を公開している教習所もあります。
答え合わせもできて使いやすく、なにより自動車教習所が提供しているので、信頼性が高いのもポイントです。ただ、前述の通り都道府県によって問題の傾向が異なることがある点については忘れないでおきましょう。
その他、教習所によってはコンピューターを使って勉強できるところもあります。次の教習までの空き時間などに活用してみましょう。
ここまで述べた以外の勉強方法だと、市販のテキストを利用する方法もあります。ただし、今では上記のようにインターネットやスマートフォンアプリなど、無料で学べる方法があるため、こだわりがなければわざわざお金を出してテキストを買う必要はないかもしれません。
仮免学科試験合格のためには授業以外の勉強も欠かせませんが、授業も一番の試験勉強になります。学科教習を行う教官の中には、頻出部分や出題傾向を教えてくれる方もいるため、教えてもらった価値ある情報は必ずノートをとっておきましょう。
効果測定もしっかり行う
効果測定とは、仮免学科試験の模擬テストのようなもので、名前の通り、これまでに受けてきた授業の効果を測るために行われます。
効果測定は模擬テストであるため、高校の模試のように受けない自由があると考えている人がいるようですが、この考えは間違いで、仮免学科試験の前および本免学科試験の前には必ず受けなければいけません。
この効果測定に合格しておかなければ、仮免学科試験の受験資格が認められません。修了検定(仮免取得のための技能検定)は効果測定が不合格でも受験資格は認められるため、修了検定に合格した後に効果測定をパスし、仮免学科試験を受けて仮免許を取得することも可能です。
ただし、日程が変則的になってしまうため、なるべく仮免学科試験と修了検定の前に効果測定を終えておいた方がいいでしょう。
仮免試験の効果測定は仮免試験と同じ方式で、30分の試験時間で全50問の文章問題を解きます。出題範囲は仮免学科試験に準じ、合格ラインも仮免学科試験と同じく90%です。つまり、全50問のうち、45問以上の正解で合格です。
効果測定では、受験後にその場で答え合わせを行います。問題用紙は持ち帰れませんが、間違えた問題のメモは取れるので、自分の苦手なところの傾向をつかむためにも、間違えた箇所をメモしておくのがおすすめです。
もし効果測定が不合格だった場合は再び受験しなければいけませんが、その際には再受験料が必要です。再受験料は教習所によって異なっていますが、多くは1回につき3,000円程度に設定されています。
複数回受験した分だけ再受験料が必要になるため、なるべく少ない回数で合格しましょう。効果測定は人によっては10回近く不合格になる人もいます。
仮免や本免の学科試験と同じで、学力やIQの高い人が受かりやすいとは限りません。中には複数回の不合格で自信を失い、免許の取得を諦める人もいるようですが、不合格になった分だけ勉強になるテストでもあります。
というのも、効果測定で使われるテキストは決まった種類しか用意されていないので、テキストを種類分1周したら、また最初のテキストから繰り返し使われていきます。
つまり、効果測定は繰り返し受験していればよほどのことがない限り、いつかは合格できるということです。しかも、効果測定で出た問題は仮免学科試験にも使われることがあるため、恰好のテスト勉強になります。反復練習にもなるため、効果測定をしっかり受けていれば、今後の学科試験が楽になるでしょう。
技能検定はどのようなことをするの?
仮免許の技能試験とは、試験官を助手席に乗せて運転の技術をチェックする試験です。教習所の敷地内を10分~15分周回し、発信方法、停車方法、直線道路、坂道発進、踏切通過、クランク、S字、そして到着時の確認などを審査されます。
減点方式で採点が行われ100点中70点で合格となります。
まとめ
免許の学科試験は問題形式が独特なうえに、仮免学科試験では暗記するべき項目が多くあります。
本免許試験でも第1段階の内容は多く出題されるため、仮免学科試験の勉強を頑張っておけば後々楽になります。勉強が苦しい時には同じ教習所の仲間たちと励ましあって乗り切りましょう。合格を祈っています!
よくある質問
■仮免学科と本免学科はどちらが難しい?
仮免許試験と本試験の学科は、問題数や時間、合格点などが違います。
それぞれの違いは以下をご覧ください。
・仮免許学科試験
制限時間 30分
問題数 50問
合格ライン 45問以上
・本免許学科試験
制限時間 50分
問題数 95問
合格ライン 90点
問題数の多さと合格点の高さからいって、95問中90点が合格ラインの本免許の学科試験の方が難しいでしょう。
■仮免学科試験に落ちたらどうなる?
仮免許の学科試験は50問中45問以上で合格となるため、基準に達していない場合は不合格です。試験結果はすぐにわかるので、合格するまで受験し、その都度受験料(2,900円)がかかります。
また、技能試験に合格してから3ヶ月以内に取得しなければいけないと規定があります。もし不合格になってしまったら、再度過去問を勉強し、早めに受験するようにしましょう。
■仮免学科試験と技能試験の合格率は?
仮免の学科試験と技能試験の合格率はどのくらいなのでしょうか。警視庁が取りまとめた資料によると、直近3年における仮免の学科試験と技能試験の合格率は以下のようになります。年度によって合格率の違いはあるものの、それぞれの合格率の平均は以下のようになります。
仮免学科合格率平均:86.9%
仮免技能試験合格率平均:76.6%
参考資料:運転免許統計 令和3年版
どちらも、7割以上の合格率なので、傾向と対策を反復学習し、一発で合格できるように勉強をすることが大切です。技能試験の場合、限られた時間での教習になるため、わからない部分などは積極的に指導員に聞き、シミレーションを重ねて試験に臨むようにしましょう。