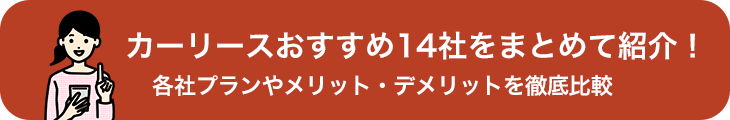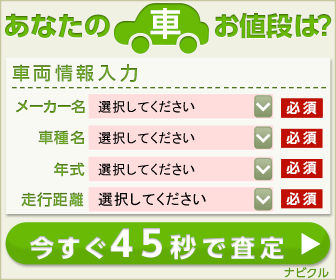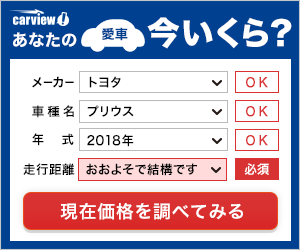車のバッテリーの役割と構造

■自動車用のバッテリーには2つの主な役割がある

そもそも、自動車用バッテリーの役割とはなんでしょうか?
自動車のバッテリーには主に2つの役割があります。
・エンジンが始動する際に用いられる「セルモーター」に電気を供給するという役割。
・普段は何気なく使っているカーナビやエアコン、夜間の照明や右左折時に点灯するランプなどといった電子機器に電気を供給する役割。
そして、エンジンが回転する力の一部を電力に変換し、車に必要な電力を供給する装置がオルタネーターです。
余った電力はバッテリーに蓄えられ、エンジン始動の際のセルモーターの電源に使われるため、非常に重要な装置といえます。
バッテリー上がりの原因とは?

バッテリーが上がってしまう原因には、どのようなものがあるでしょうか。ランプ等の消し忘れはもちろん言われるところですが、原因となる候補をいくつか例示します。

■1、ライトの付けっ放し

バッテリーが上がってしまう理由として最も多いのが、ライトの付けっ放しによるバッテリー上がりです。
エンジンを止めた後にうっかりヘッドライトや室内灯を点けっぱなしで車から離れてしまうこともあると思うのですが、そういった場合に発生してしまいます。
これは、車に搭載されているバッテリーの電力が消費されてしまうので、車の電力が無くなってしまうことで発生します。
その原因はバッテリーの役割から理解できます。
バッテリーの役割は、エンジンを始動する際に必要となる電力を、短時間で放電するという機能と、エンジン始動以降は、オルタネーターによって発生した電力を充電し蓄えてくおくという機能があります。
エンジン停止の状態では、発電機による発電は出来ません。ですので、その間はバッテリーに蓄電されていたる発電のみでライトやエアコン等に電力を供給しているという状態です。
エンジンを止めた状態で長時間ライトを点けたままにしておくと、蓄電されていた電力が消費されて、結果として電力がなくなるので、バッテリーが上がってしまいます。
■2、車を使う頻度が少ない場合
普段は車に乗らずたまにしか車の使わないという場合でもバッテリー上がりの可能性があります。
これは、バッテリーの自然放電が原因によるものです。
車の装備は使用していない状態であっても微量ではありますが、電気を消費しています。なので、エンジン始動後の発電を行わないのであれば、蓄電された電力から自然放電が進んでしまい、最終的にバッテリーが上がるという事につながります。
■3、季節による要因:冬の時期はバッテリー上がりが多い

これまでご説明してきた理由以外のバッテリー上がりの要因として、季節要因による可能性があることをご存知でしょうか?
これは、車載バッテリーの中のバッテリー液の性能の変化によるものです。バッテリー液は希硫酸という液体で満たされているのですが、この液体は温度が下がると性能が落ちるという傾向があります。
そうなると、冬の寒い時期になると自然と性能が落ちてしまうケースもあるので、結果としてバッテリーが上がりやすくなってしまいます。
バッテリー上がりの症状
車のバッテリーが上がってしまった際には、どのような症状が起きてしまうでしょうか?
一般的には以下の2つの要素があります。
■エンジンが始動しない
バッテリーが上がっている状態では、エンジンを始動するときに必要な電気エネルギーを供給する事が出来ないので、エンジンがかかりません。
バッテリー上がりの対処法

バッテリーが上がってしまった際には、どのような対処をすべきなのでしょうか。
基本的には、もう一台車を用意して、その車のバッテリーからブースターケーブルと呼ばれるケーブルを使って電力を分ける方法や、ジャンピングスタートという方法を用いて対応する事が可能です。
■救援車を使う
バッテリーが上がった際には、救援車を用いたジャンピングスタートという方法で対処する事が可能です。救援車を用いる際には、電圧が12Vの乗用車を用意します。
そして、ジャンピングスタートを行うための2つの車を繋ぐ、ブースターケーブルと呼ばれるケーブルが必要です。
ジャンピングスタートを行う際には、赤と黒のケーブルをそれぞれ2つの車に接続し、救援車のエンジンを始動させて相手の車にエネルギーを送る形をとります。
ブースターケーブルの接続
まずは、救援車のエンジンを止めて、ブースターケーブルを繋ぎます。不慮の事故を防ぐ為にも、安全な場所を確保するようにしてください。
赤のプラスケーブルをバッテリーが上がった車のプラス端子に繋いで、次に救援車のプラス端子にケーブルを繋ぎます。
赤のケーブルをつないだ後に黒のマイナスケーブルを救援車のマイナス端子に繋いで、最後に自分の車のマイナス端子にケーブルを繋ぐという手順で進めていきます。
作業を行う上でケーブルが破損していないか、接続する金属の部品部分を損傷しないように注意深く作業をするようにしてください。
救援車のエンジン始動
救援車のサイドブレーキをしっかりと掛けてからエンジンを始動してエネルギーを送る準備を進めます。トランスミッションは、ATであればパーキング、MTであればニュートラルに合わせます。適切な電力供給に際しては、救援車のエンジンの回転数を2000〜3000くらいで調整すると効率的に事が運びます。
自分の車のエンジン始動
救援車からの電力供給を受けて、今度は自分の車のエンジンを始動させていきます。ケーブルは繋がったままの状態で、エンジンを始動させます。問題なく自分の車のエンジンが始動すれば、応急措置はとりあえずは完了です。
ブースターケーブルを外す
無事に自身の車のエンジンが始動したら、ケーブルを外して片付けをしていきます。ケーブルの取り外す順番は、最初に接続した際とは逆になり、黒のケーブルから外して、赤いケーブルを外すという順で進めます。
このようにジャッピングスタートで救援車を用いてエンジンを始動させることは出来ます。
ケーブルを外して無事エンジンが始動した後は、バッテリー自体の寿命やバッテリーそのものが損傷している可能性もあるので、即座に点検を行うようにしてください。
■ジャンプスターターを使う

ジャンプスターターは蓄電機能を持っているので、バッテリーが上がった際に自分で対処する事が出来ます。
普段から車に常備させておけば不慮の故障の際にも、柔軟に対処していく事が出来るので是非検討してみてください。
ジャンプスターターのケーブルをバッテリーに接続する
基本的な手順ですが、ジャンプスターターに付属されているケーブルを、車のバッテリーに接続して充電を行って対処するという形で対応していきます。
ケーブルを接続する際には、赤いプラスコードを車のプラス端子に接続し、黒いマイナスコードをマイナス端子に接続します。その後に、ジャンピングスターター本体にケーブルを接続したら事前準備は完了です。
ジャンプスターターの電源を入れて、エンジン始動
赤と黒のケーブルとバッテリーとの接続が終わったら、ジャンプスターターを接続して送電の準備をします。ジャンプスターターの電源を入れてからエンジンが掛かれば、対処は完了になります。ただ、ジャンプスターターの電源を入れてからエンジン始動までには、数分時間を置いてから行うようにしてください。
ジャンプスターターのケーブルを外す
無事に車のエンジンが掛かった事を確認出来たら、後片付けをしていきます。ジャンプスターターの電源を切って、バッテリーのマイナス端子、プラス端子の順に接続したケーブルを外します。
エンジンを継続始動させて、バッテリーを充電する
バッテリーが上がっていた状態の車は、 エンジンがかかっているとはいえ、まだ十分な電力がない状態です。そのような状況下ではもしエンジンが止まると再始動出来ない事もあります。ですので、エンジン始動後しばらくはエンジンを掛けっぱなしにして、電力を蓄えるようにしてください。
ジャンプスターターでのバッテリー上がりの対処後は、エンジンの不調や故障の可能性もありますので、即時に点検を行うようにしてください。
■ロードサービスを利用する

JAF(日本自動車連盟)のケースであれば、ロードサービスを依頼する際には救援コールに連絡します。連絡する際には、電話やスマートフ、パソコンや携帯電話のメール、さらにFAXでも救援依頼を行うことが出来ます。
救援窓口に繋がったら、故障した車両がある位置(住所がわかっていれば最高ですが、地名や目印となるものでも可能)を伝えます。
次に、車の車名、車体の色やナンバー、そしてトラブル内容の詳細を伝えます。最後にJAF会員か否かを伝えます。対応にかかる時間は、場所や混み具合によって異なりますので、注意が必要です。
バッテリー上がりでの対応は、ジャンピングスタートの対応を行った後に、料金を支払います。
JAF会員になっていれば、一般道・高速道路でのバッテリー上がりの作業は無料です。
非会員の場合は、一般道の場合は約1万3000円~約1万5000円。高速道路では約1万5000円~約2万5000円で別途高速道路料金が必要になります。
交換時期:バッテリーの寿命はどのくらい?
バッテリーの寿命は、使用状況によっても異なりますが、平均は2~3年位です。
新車で購入した場合は、最初の車検の時期が交換の目安になります。バッテリー交換をディーラーで行なってもらっている場合は、整備点検記録簿に履歴が記載されますので、その日付から3年を目安に交換が望ましいでしょう。
自分でバッテリーを交換する場合の方法

バッテリー上がりの対処を自分で行うとなった際には、ゴム手袋や、スパナ、ドライバーや保護メガネを用意します。また、バッテリーの交換作業を行う際には、事前に安全の為にエンジンが停止している事を目視で確認して、さらに車のキーを抜いて、不慮の事故が起こらないように環境を整えてください。
バッテリー交換の手順としては、まずはバッテリーに接続されているマイナス端子のケーブルを外していきます。その次に、プラス端子のケーブルを外して、バッテリーを固定する為に取り付けられている金具を外していきます。精密機器ですので、丁寧に作業を進めていってください。
金具を無事に外せたら、バッテリーを取り外します。ゆっくりとまっすぐ上に持ち上げていくと、バッテリーは外す事が出来ます。バッテリー交換は頻度が多い訳ではないので、新しいバッテリーに交換する前には、周辺部分の清掃もしておくと、より寿命を長引かせる事につながります。新品のバッテリーを設置する際には、それぞれの極性が合っているかを確認して、取り付け金具で固定していきます。
固定が完了した後は、プラス端子のケーブル、続いてマイナス端子のケーブルという順で取り付けて完了です。
バッテリー交換にかかる費用
バッテリー交換にかかる費用ですが、搭載されているバッテリーの大きさや希望する性能によって価格は異なります。ただ、価格の目安としてはだいたい3,000円~2万円ぐらいが一般的です。
カー用品店でバッテリー交換を行うとなった際には、500円程からが相場となっています。
おすすめのバッテリー
いくつかオススメのバッテリーをご紹介します。